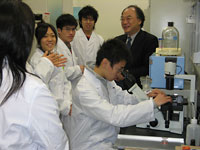 第1日目(1月4日(水))
第1日目(1月4日(水))
開講式は、部門長から挨拶と研究所の研究内容について解説を受けた。
講義「生きていること」では、講師が、DNAを含め生物の基本的な構造から個体の構成まで。
実験1「タンパク質の電気泳動」では、電気泳動の原理が難しかったことと、マイクロピペットの操作が初めてのため、手間取った生徒もいた。
実験2「ニワトリ胚の観察」では、発生5日目の胚を取り出し、観察・解剖を行った。また、発生の進んだ胚も取り出し、観察・解剖を行った。高校では、資料集などに写真はあるが、実物を見るのは初めてで、参加生徒も引率した私も感動した。
ミーティングでは、自己紹介後、参加の印象など、意見交換を行う。また、実験・講義の内容についての質問などに答え、詳しい説明もする。
第2日目(1月5日(木))
講義「生きること」では、DNAを始めとする生命を生かすしくみと、より良く生きるための神経系の働きについて講義を受ける。
実験3「神経細胞の培養」では、ニワトリの胚から、神経組織を取り出し、解離して、培養基に移す。
講義「神経細胞のシナプスの仕組み」では、シナプスの構造と働きについて、講義を受ける。
実験4「神経細胞の形態観察」では、ラットの小脳のブルンキエ細胞の蛍光染色標本を蛍光顕微鏡で観察する。特殊な神経細胞を観察することができた。
実験5「神経細胞の電気活動計測」では、培養した神経細胞にガラス電極をマニピュレータで挿入する。顕微鏡下で操作する難しさを体験した。また、培養した神経細胞が自分で回路を形成して情報を交換するときの電気的な変化を観察する。また、培養細胞間の電気的な信号のやり取りの情報をロボットの動きに変換し、ロボットのセンサーからの情報を神経回路に戻して、その変化をロボットの動きに変換する実験を見学した。
講義「筋肉細胞と軸索輸送の仕組み」では、筋収縮のしくみと、軸索中を物質が運ばれるしくみの講義を受ける。
実験6「キネシン運動の観察」では、微小管を作るキネシンタンパクの運動を顕微鏡下で観察する。
実験7「メダカの神経細胞の観察」では、遺伝子操作を行ったメダカを観察した。実験動物としての可能性を知った。
懇親会では、多くの研究者が参加生徒のために集まり、有益な話を聞くことができた。高校生の質問に丁寧に回答していただいた。
ミーティングでは、講義・実験の感想などを発表する。懇親会での話題で、生命倫理の事を述べた生徒がいたので、この話題で話しを進める。脳死臓器移植・クローン人間の話題にも広がった。
第3日目 1月6日(金)
実験「培養神経細胞の観察」では、前日に培養を始めた神経細胞の観察を行う。培養時間が足りなかったので、軸索の伸び方が少なかった。観察はできたので、その変化には驚いた。
講義「神経細胞の微細構造」では、シナプスの構造など講義を受けた。
講義「細胞研究の新しいアプローチ」では、電子顕微鏡による新しい研究の内容と、表面プラズモンの現象を利用した顕微鏡による研究について講義を受けた。
実験8「電子顕微鏡観察」では、CTの画像解析の技術を使った電子顕微鏡の画像を見る。シナプスの立体構造が観察できた。
実験9「光を使った新しい計測法」では、表面プラズモンの原理を使った顕微鏡での研究について実物を見ながら、その原理と研究の方向を知った。
修了式は、昼食をとりながら、質疑などとまとめを行う。発表として、生徒が一人ずつ感想や将来の希望、研究についての抱負などを述べ、その後、修了証を副部門長より手渡された。最後にお礼の言葉も皆で言うことができた。研究所の正門で記念写真も撮影し、別れを惜しんだ。