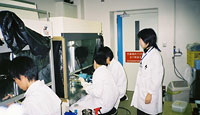 第1日目(12月24日)
第1日目(12月24日)
【プログラム内容】沿岸環境科学について(1)海洋生態系の基本的仕組み、(2)マイクロビアルループと捕食食物連鎖、(3)食物連鎖と生態系汚染、の3つの講義および沿岸環境科学研究センターの概要説明と実験概要説明
【参加者の様子】1日目は講義が3つ連続してあり、遠方からきた参加者は疲労のため、後半集中力が続かなくなっていた。講義内容については専門的ではあるが、わかりやすい説明で、概ね理解できたと感じた。夕食後のミーティングでは自己紹介や学校紹介などを行い、参加者同士の親睦を深めた。最初は生徒間での会話はほとんどなかったが、徐々にうちとけていった。ミーティング終了後、翌日からのデータ整理やプレゼンテーションに備えて、簡単なパソコン操作の講習会を行った。参加者の中にはほとんど操作ができないものもおり、翌日の班分けの際、パソコン操作のできる生徒を各班に振り分けるよう配慮した。
第2日目(12月25日)
【プログラム内容】プランクトンについての講義と水質分析器の見学のあと、3班に分かれ(1)微生物量測定の準備および全菌数カウント、(2)固定プランクトン試料の光学顕微鏡を用いての観察および計数、(3)電子顕微鏡によるプランクトン観察、の3つの実習を同時進行ですべて行った。
【参加者の様子】2日目は実習が3つ連続して行われ、特に午後は休憩時間もほとんど取れないままの状態が続いたため、実習終了時には集中力がきれてしまい、培養準備の作業で失敗が続く生徒や、講師の説明を的確に聞き取ることができなくなる参加者もおり、非常に疲労していた。
懇親会は研究者との交流を深めるチャンスであったが、会場が変更になり、すこし手狭になったことで大学のスタッフが1箇所にかたまってしまい、実習の疲労も手伝って、積極的に講師との交流がはかれない生徒もみられた。しかし積極的に動き回ることができた生徒にとっては研究内容などについての質問を行うなど、有意義な時間になった。
ミーティング後は翌日の発表に備えて深夜までパソコンを操作し、班ごとに協力してデータを整理していた。
第3日目(12月26日)
【プログラム内容】生物環境試料バンクをはじめとする施設見学のあと、生菌数をカウントした。その後、実習から得られたデータを整理し、班ごとにパワーポイントを用いて発表を行った。
【参加者の様子】施設見学では様々な試料や機器をみることができ、生徒は興味を示していた。講義、実習後、午後からの発表に備えて班ごとに協力して頑張っていた。
午後からは全員緊張しながらも、短い時間でまとめた内容をパワーポイントを用いて発表した。どの班もよい発表内容であった。