 サイエンスキャンプの会場は、いずれも日本を代表する最先端の研究所です。どの研究所も、最先端の科学を高校生が無理なく体験できるよう、独自に工夫したプログラムを準備しています。それぞれのプログラムには、一貫したテーマのもと、講義や実験・実習などがうまく組み合わされています。実習はいずれも人気が高く、大型実験棟の特別な研究装置の体験や、さまざまな超精密機器類のオペレート、そして付属施設でのフィールドワークなど、その内容はじつにバラエティーに富んだものとなっています。 サイエンスキャンプの会場は、いずれも日本を代表する最先端の研究所です。どの研究所も、最先端の科学を高校生が無理なく体験できるよう、独自に工夫したプログラムを準備しています。それぞれのプログラムには、一貫したテーマのもと、講義や実験・実習などがうまく組み合わされています。実習はいずれも人気が高く、大型実験棟の特別な研究装置の体験や、さまざまな超精密機器類のオペレート、そして付属施設でのフィールドワークなど、その内容はじつにバラエティーに富んだものとなっています。
サイエンサキャンプがスタートした当初は、研究者と高校教諭による綿密な打ち合わせが行われました。そして最先端の科学技術を高校生が理解できるような、効果的で魅力あふれるプログラム作りを目指しました。現在は、どの研究所もこれまでに蓄積された経験とノウハウを活かし、個性的なプログラム提供が行われています。
夏休み中のキャンプ初日には、研究者や事務官などが和やかなムードのなか、参加者を温かく迎え入れてくれます。そして三日間のキャンプでは、多くの研究者や事務官などが連携し、十分な心配りのもと、プログラムが滞りなく進行するように参加者を指導・サポートします。
過去7年間で、32の研究所がサイエンスキャンプの会場となりました。そのうち2001年は、25の研究所が会場となり、なんと300名以上の研究者と80名以上の事務官が高校生のサポートに関わりました。
プログラムの分野は、自然科学、物質材料、情報電子、航空宇宙、海洋科学、地球科学、産業技術、原子力、農業、食品、医薬など多岐に渡りました。
それでは、サイエンスキャンプ2001の会場となった25の研究所を紹介します。
 自然科学 自然科学
理化学研究所は、日本で唯一の自然科学の総合研究所です。物理学・化学・工学・生物科学・医科学等幅広い分野にわたり、基礎研究から応用研究まで多様な研究活動を展開しています。キャンプでは、実際の研究現場で、微生物観察と微生物の進化の道筋の考察、IT卓上加工機を使用したナノテクノロジー加工実習、プログラム細胞死のしくみなどの研究テーマの実習を行いました。
物質材料
物質・材料研究機構は、金属材料技術研究所と無機材質研究所が統合してできた新しい研究機構で、新時代を担う新しい構造材料の開発研究、セラミックスの研究に取り組んでいます。キャンプでは、引張試験機・衝撃試験機の実験、走査型電子顕微鏡による材料組織の観察、ダイヤモンドの製作などを通して、未来の新材料の開発を目指した実習を行いました。
情報電子
通信総合研究所 本所は、電波・光に関する研究を基盤として情報通信に関する基礎から応用までの幅広い先端研究開発を進めています。キャンプでは、次世代インターネット、原子周波数標準、通信用デバイスについて先端科学技術の一端を実際に手を触れて実習を行いました。
 航空宇宙 航空宇宙
航空宇宙技術研究所は、航空技術と宇宙技術の向上を図る研究や試験を行っています。次世代超音速機(SST)や成層圏飛行船、宇宙輸送システムなどのプロジェクト研究、航空安全や宇宙環境安全利用技術、数値シミュレーション技術などの研究を行っています。キャンプでは、航空宇宙開発の魅力を知る成層圏飛行船・宇宙往還機・ジェットエンジンなどのセミナー、スーパーコンピュータ操作、フライトシミュレーター操縦などの実習を行いました。
宇宙開発事業団は、人工衛星(宇宙実験や宇宙ステーション)、人工衛星打上げ用ロケットの開発や打上げ、追跡についての方法、施設、設備の開発を行っています。キャンプの会場となる筑波宇宙センターには、宇宙遊泳の訓練プール、宇宙ステーション管制センター、人工衛星の機能試験を行うスペースチャンバなどの施設があります。キャンプでは、国際宇宙ステーション、ロケット、人工衛星などのセミナー、衛星の実物大模型、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」の実物大モデルの見学、小型ロケットの制作と打ち上げ・回収などの実習を行いました。
海洋科学
港湾空港技術研究所は、港湾・海岸・空港分野における基礎的な調査、研究や技術の開発、事業の実施についての研究や技術の開発を行っています。キャンプでは、実際の研究現場で、海岸や港に棲む生物の活動、地震による液状化現象、海中の構造物などの研究テーマに取り組む実習を行いました。
海洋科学技術センターは、地球温暖化や巨大地震の発生などの地球変動の予測をめざした研究や、深海に棲む生物や海洋エネルギー利用など、海洋についてのさまざまな研究に取り組んでいます。特に深海調査船「しんかい6500」の活動や「H-IIロケットエンジン部」調査などはよく知られています。キャンプでは、深海と21世紀の地球にテーマをしぼり、深海6500メートルの世界・深海の生物・沈没船の探査法・地球環境と海洋などのセミナー、水中ロボットによる生物観察、圧力体験実験、体験潜水などの実習を行いました。
地球科学
気象研究所は、気象・地象・水象に関する現象の解明と予測の研究や関連技術の開発を行っています。キャンプでは、地球ではどんなことがおこっているのか、いろいろな自然現象(気象・地象・水象)を知る講義、実験、観測などの実習を行いました。
防災科学技術研究所は、地震・火山噴火・大雨・地すべり・雪氷等の災害から人命を守り、災害の教訓を生かして、災害に強い社会の実現を目指すためのさまざまな研究に取り組んでいます。さらに、地球環境の変化とそれにともなう災害の予測まで研究活動を展開しています。キャンプでは、災害の起こる仕組みや自然現象と災害の発生するメカニズムなどのセミナー、最先端のマルチパラメターレーダーで雲の観察、地震液状化現象・なだれの自然災害現象を再現する実験などの実習を行いました。
 産業技術総合研究所 北海道センター 北海道地質調査連携研究体は、地質の調査を行い、地球の歴史、エネルギー・資源、地震、火山等の自然災害、地球環境を総合的に調査・研究しています。また、生活に必要な地球科学情報を発信しています。キャンプでは、北海道を舞台に、地質調査の仕方を習得し、有珠山、昭和新山周辺等の岩石・地層の観察、活断層の観察等のフィールドワーク、地球科学情報の収集作業などの実習を行いました。 産業技術総合研究所 北海道センター 北海道地質調査連携研究体は、地質の調査を行い、地球の歴史、エネルギー・資源、地震、火山等の自然災害、地球環境を総合的に調査・研究しています。また、生活に必要な地球科学情報を発信しています。キャンプでは、北海道を舞台に、地質調査の仕方を習得し、有珠山、昭和新山周辺等の岩石・地層の観察、活断層の観察等のフィールドワーク、地球科学情報の収集作業などの実習を行いました。
国立環境研究所は、地球温暖化、オゾン層破壊、環境ホルモン、生物多様性減少、流域単位での持続可能な発展、都市大気環境汚染などの地球環境問題に対応するため、いろいろな分野から地球環境研究に取り組んでいます。キャンプでは、温室効果ガス濃度等の観測を行っている北海道の落石岬ステーションでフィールドワークを行い、湿原植物の光合成能力を調査し、温室効果ガスを考察する実習を行いました。
産業技術
 産業技術総合研究所は、旧工業技術院傘下15研究所と計量研修所が再編されてできた研究所です。多岐にわたる分野の研究者集団の融合と創造性の発揮による研究活動を通じて、新たな技術シーズの創出、産業技術力の向上や新規産業の創出などを行っています。つくばセンターでのキャンプは、情報技術、エレクトロニクス、エネルギー技術などについて、実際の研究現場で模型スターリングエンジン製作、太陽電池製作、プログラムによるデジタル回路製作などの研究テーマに取り組む実習を行いました。 産業技術総合研究所は、旧工業技術院傘下15研究所と計量研修所が再編されてできた研究所です。多岐にわたる分野の研究者集団の融合と創造性の発揮による研究活動を通じて、新たな技術シーズの創出、産業技術力の向上や新規産業の創出などを行っています。つくばセンターでのキャンプは、情報技術、エレクトロニクス、エネルギー技術などについて、実際の研究現場で模型スターリングエンジン製作、太陽電池製作、プログラムによるデジタル回路製作などの研究テーマに取り組む実習を行いました。
産業技術総合研究所 北海道センターは、研究の大きな柱としてバイオ・エネルギー・材料に関する研究を行っています。低温環境下で働く微生物の利用やタンパク質の構造や機能の解明、メタンハイドレートなどの新エネルギー資源の利用、微小重力下での高品質材料の製造など、新しい技術の開発を目指しています。キャンプでは、北の大地―自然と科学を探るとして、遺伝子工学、バイオ技術、無重力実験施設の見学など最先端の科学技術の実習を行いました。
原子力
日本原子力研究所は、原子力分野を専門とした日本における総合研究機関です。核融合や高温ガス炉などの未来の原子力エネルギーの開発、原子力施設や環境の安全性、放射線利用の研究開発などを行っています。キャンプでは、核融合の研究開発現場の見学や自然放射線の測定、放射線の軌跡を観察できる霧箱の作成、マニピュレータ操作、研究用原子炉シミュレータ運転などの実習を行いました。
核燃料サイクル開発機構は、エネルギーの安定供給確保のために、新しい原子炉(高速増殖炉)の開発と核燃料サイクル技術の開発を進めています。中でもキャンプ会場となる大洗工学センターは、高速増殖炉の実用化に向けた研究開発を行っています。キャンプでは、ナトリウムの特性を実験や計算で確かめるといった基礎的な分野のほか、原子炉の模擬運転体験等を通して、第一線の研究開発活動を行いました。
農業
 農業技術研究機構 中央農業総合研究センターは、水田や畑の生産力を発展させ、安全で高品質の食料を安定的に供給する技術を開発し、地球人口の急増と食料需要の逼迫に備えること、農業を担う人を支え、美しく豊かな農村づくりに役立つ技術と方法を研究し、日本の文化の源流である農業・農村を守り支えることを使命としています。キャンプでは、土壌の断面観察と分析、土壌線虫の観察、雑草の観察などの実習を行いました。 農業技術研究機構 中央農業総合研究センターは、水田や畑の生産力を発展させ、安全で高品質の食料を安定的に供給する技術を開発し、地球人口の急増と食料需要の逼迫に備えること、農業を担う人を支え、美しく豊かな農村づくりに役立つ技術と方法を研究し、日本の文化の源流である農業・農村を守り支えることを使命としています。キャンプでは、土壌の断面観察と分析、土壌線虫の観察、雑草の観察などの実習を行いました。
農業技術研究機構 作物研究所は、稲、麦、大豆、さつまいもなどの基幹作物に加え、ゴマ、アマランサスなどの資源作物全般を対象として、品種、栽培生理、品質成分の研究を行い、画期的新品種の育成や低コスト・高品質栽培技術の開発などのニーズに答えようとしています。キャンプでは、世界の米の炊飯・試食、麺打ち、水田圃場の見学、稲の交配などの実習を行いました。
農業技術研究機構 果樹研究所は、くだものを研究対象とする日本を代表する研究所です。リンゴ「ふじ」、日本ナシ「幸水」、カンキツ「清見」、モモ「あかつき」等の数々の品種育成、バイオテクノロジーを駆使した育種技術の開発、機能性成分に関する果樹の栽培・病害虫防除についての技術開発など、果樹のあらゆる分野の研究を行っています。キャンプでは、実際にくだものに触れながら、収穫作業の大変さ、果樹研究のおもしろさなどを体験しました。
農業技術研究機構 動物衛生研究所は、家畜を始めとする動物の健康を守るため、動物の病気について診断・予防・治療法の研究・開発を行っています。キャンプでは、動物の病気について理解するため、実際に動物に触れ、動物の健康状態を把握しました。また、病気を引き起こす原因の一つであるウイルスの性状を検査し、構造や形を電子顕微鏡で観察し、動物の健康保持や病気の予防について実習し、動物のお医者さんを体験しました。
農業環境技術研究所は、将来にわたって安全な食べ物を生産していくため、土・水・大気を健全な形で保全し、植物相や昆虫と共生する農業を目指した研究を行っています。キャンプでは、農薬が水生生物に与える影響、植物が土壌中の養分を吸収する方法、農耕地から発生する温室効果ガスを測定するなどの研究テーマに、研究者がどのように問題解決に取り組んでいるかを実習で体験しました。
農業工学研究所は、食料の安定的生産のための農地やかんがい排水施設等の整備、人々の快適な生活のための環境整備と、農業・農村の持つ多面的機能の解明・評価を行うのに必要な工学的研究を行っています。「豊かで人と自然にやさしい農村の振興」をテーマに研究を展開しています。キャンプでは、農村の人々にとって大切な「私たちの村、私たちの水」をテーマに、アイマークレコーダを用いたバーチャル農村探検、水路でのメダカの動きを知るためのフィールドワーク、人工降雨装置を用いた雨水の動きの観察、アオコ発生のコンピュータ・シミュレーションなどの実習を行いました。
 森林総合研究所は、森林・林業・木材産業にかかわる中核的な研究機関として森や樹木のしくみと役割を総合的に研究しています。キャンプでは、木材や葉のフィトンチッドの香り成分の採取、樹木のポリフェノール成分の抽出など木の成分を調べる実習や筑波山の標高別植生や鳥類の分布のフィールドワーク、地理情報システムの活用など森のコンピュータ測定などの実習を行いました。 森林総合研究所は、森林・林業・木材産業にかかわる中核的な研究機関として森や樹木のしくみと役割を総合的に研究しています。キャンプでは、木材や葉のフィトンチッドの香り成分の採取、樹木のポリフェノール成分の抽出など木の成分を調べる実習や筑波山の標高別植生や鳥類の分布のフィールドワーク、地理情報システムの活用など森のコンピュータ測定などの実習を行いました。
食品
食品総合研究所は、食品研究の専門機関として、食品成分の機能性評価や分析技術の高度化など、食と健康の科学的解析、食料の安全性確保と革新的な流通・加工技術の開発、新たな食品機能の発掘と利用など、「食」に係る科学技術の幅広い研究を行っています。キャンプでは、果樹の糖度測定、食品成分の化学構造を核磁気共鳴分析装置で解析、ドライアイスフリージング法を用いた加工食品作りなどの実習を行いました。
医薬
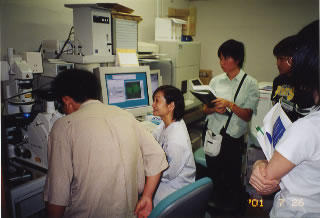 国立医薬品食品衛生研究所は、医薬品、食品、化学物資、家庭用品、医療用具、毒物及び劇物など国民生活に密接に関連する化学物質の試験や研究、薬用植物の栽培指導、研究などを行っています。キャンプでは、主に薬品、生物薬品、環境衛生化学、生薬関係の研究や化学物質に関する情報検索、実験動物がどのように科学の進歩に役割を果たしているのかなどの実習を行いました。最終日には希望する研究部署の見学を行いました。 国立医薬品食品衛生研究所は、医薬品、食品、化学物資、家庭用品、医療用具、毒物及び劇物など国民生活に密接に関連する化学物質の試験や研究、薬用植物の栽培指導、研究などを行っています。キャンプでは、主に薬品、生物薬品、環境衛生化学、生薬関係の研究や化学物質に関する情報検索、実験動物がどのように科学の進歩に役割を果たしているのかなどの実習を行いました。最終日には希望する研究部署の見学を行いました。
放射線医学総合研究所は、放射線の人体に与える影響や放射線による人体の障害の予防、診断、治療や放射線の医学利用に関する研究開発を行っています。キャンプでは、「放射線の医学利用とその基礎」をテーマに放射線がどのように治療、診断に利用されているかを、重粒子線がん治療装置の見学、遺伝子診断というライフサイエンス実験、加速器による元素分析などを通し、研究の基礎となる生物や環境への影響について最先端の実習を行いました。
|

