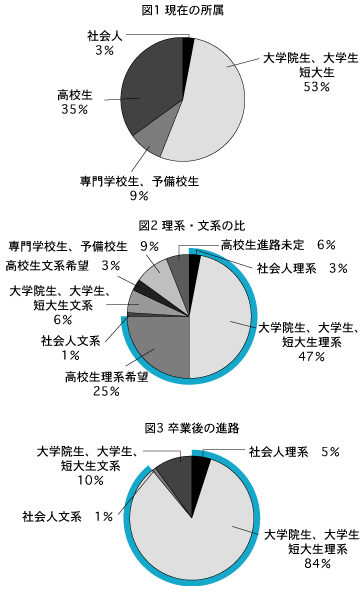 第1回のサイエンスキャンプ1995から第5回のサイエンスキャンプ1999までに参加した高校生・高等専門学校生にアンケートの協力をお願いしたところ、半数近くの577名から回答をいただきました。 第1回のサイエンスキャンプ1995から第5回のサイエンスキャンプ1999までに参加した高校生・高等専門学校生にアンケートの協力をお願いしたところ、半数近くの577名から回答をいただきました。
現在の所属は、社会人20名(3%)、大学院生・大学生・短期大学生307名(53%)、予備校生・専門学校生50名(9%)、高校生200名(35%)となっています(図1)。進路の方向を理系と文系に分けてみると、社会人理系17名(3%)、文系3名(1%)、大学院生・大学生・短期大学生理系273名(47%)、文系34名(6%)、高校生理系希望146名(25%)、文系希望17名(3%)、進路未定37名(6%)、予備校生・専門学校生50名(9%)となり(図2)、卒業後の進路に注目してみると、社会人理系17名(5%)、文系3名(1%)、大学院生・大学生・短期大学生理系273名(84%)、文系34名(10%)となっています(図3)。社会人、大学院生、大学生、短期大学生になった人の9割近くが理系です。
サイエンスキャンプに参加した高校生は、参加しなかった高校生と比べて前向きと思うという人が309名(54%)いました(図4)。キャンプへの参加は、目的意識の確定に役立つようです。最先端の科学技術は、理科の勉強の延長にあると研究者に言われ、学校で学んだ知識が研究所の実習で生きたことが嬉しかったと言う人もいます。夏休みが終わり、学校生活が始まってからは、いままで意味がわからなかった物理、化学、生物、地学など理科を学ぶ意義がわかり、勉強する目的ができたと言う人もいます。
科学技術分野への興味の持ち方の変化は、新聞で科学技術の記事をよく見るようになった人が322名(56%)、テレビで科学技術の番組をよく見るようになった人が304名(53%)、科学技術分野の雑誌・本をよく見るようになった人が284名(49%)おり、参加した人の半分を超えています。参加した高校生は、科学に対する親しみが一気に高まったようです。テレビ、新聞、雑誌などで科学情報により興味を持つようになっています。特に指導を受けた研究者がテレビに登場するのを見るとキャンプを思い出しますと言います(図5)。
現在の進路選択にあたってサイエンスキャンプから影響を受けた人は、253名(44%)、大きく影響を受けた人が156名(27%)おり、合計71%の高校生に影響を与えています。一方、あまり影響を受けなかった人は133名(23%)いました。今後の進路選択にあたってサイエンスキャンプの参加経験が与える影響は、影響する人が287名(50%)、大きく影響する人が144名(25%)おり、合計75%の高校生に影響を与えています。参加した7割近くの高校生にサイエンスキャンプへの参加は、進路を考える上で影響を与えています(図6)。高校時代は、どんな若者にとっても悩み多き時代です。とりわけ将来、進路についての悩みは大きいです。サイエンスキャンプは、最先端の研究や施設を高校生に紹介するだけでなく、講義・実習・見学を通じて高校生に自ら進むべき道を考えさせる貴重な機会となっています。
就職先として具体的に考えている職種は、研究員・研究職257名(45%)という回答が最も多く、次いで、公務員・教員108名(19%)、技術職・企業90名(16%)、医師・薬剤師76名(13%)、第一次産業9名(1%)、大学院進学7名(1%)となります。参加した高校生の5割近くが、研究員・研究職を目指しています(図7)。
サイエンスキャンプが参加した高校生に影響を与えた理由は、研究している現場で体験できたこと463名(80%)、研究者と直接話し合えたから406名(70%)、多くの人に出会えたから367名(64%)、より広い視点を得られたから302名(52%)という回答が多く、高校生にとっては、研究現場の体験と人との出会いが、大きく影響を与えています(図8)。第一線で研究に従事されている方々に直接指導を受けることが、感受性の強い高校生に強い影響を与えています。なによりも本物に触れたことが、その後の人生を考えるとき、いろいろな場面で役立つようです。また、日本各地から各学年にわたって、普通高校、工業高校、農業高校、国立高等専門学校、男子校、女子校などいろいろな学校の人が集まり、それぞれの様子が聞けてお互いに語れるなどということは、このようなキャンプの機会以外にはあまりありません。
|

