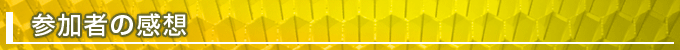細胞や遺伝子が好き(沖縄県・高等専門学校2年生)
脳を見る、知る、調べる
国立大学法人 新潟大学 脳研究所
キャンプ初日は、実際に人の脳に触れ、機能などについての説明を受けました。人の脳は予想よりもとても大きくて重く、私の手にずっしりと乗りました。この中にこの人の人格や生き方の全てが詰まっていたと考えると脳がますます神秘的に感じられました。
2日目の初めの講義では神経伝達の基本的な仕組みを学びました。今までで一番面白かった講義でした。細胞と細胞の間で起こっていることは化学反応の連続ですが、生きているということはとても不思議で、全てを化学反応だけでは説明できない気がします。
一番衝撃的で見ていて感動した実験は神経細胞を自分達で脳から取り出して、細胞一つ一つを観察したことです。親ラットから胎児を取り出し、胎児の脳を採取する一連の作業は私の脳に焼きついています。それから細胞同士をばらばらにして顕微鏡で観察しました。私たちの培養した細胞は培養直後まだ突起が伸びていなくて、2日目、1週間と生育時間の違う神経細胞も見ました。次へつなごう、つなごうという本能のようなものを感じました。
その後、受容体やシナプスなどを色分けして染めたネオンのような神経細胞や蛍光に染めた神経細胞を観察しました。蛍光に光る仕組みは抗原抗体反応を用いて染色したものだそうで、その方法がとても面白かったです。
今回のキャンプでは、沢山の知識のほかに、学ぶ楽しさを再発見しました。興味を持って、自分で調べて質問をし、その答えに納得して感動する、新しい疑問が生まれる、ということをしばらく忘れていたように思います。ここでの話はとても楽しくてしょうがなく、やはり、私は細胞や遺伝子が好きだと再認識できました。
ここで出会った仲間も、研究所の皆さんも楽しそうに実験をしてとても生き生きしていました。私も目標に向かって頑張ろうと思える素晴らしい体験でした。
科学の道につづくもの(三重県・高校1年生)
のぞいてみよう!科学技術を支える光の科学〜マイクロ波からγ線まで〜
中部大学 工学部 先進計測研究センター・工学基礎教室
キャンプに行く前、私は日々の生活に疑問を感じていました。学校の授業は大変で、でもそれが将来なんの役に立つかわからない。ただ漫然と生活し続ける未来が見えない自分・・・・・。そんな時、学校の先生からこのキャンプのことを知らされました。理系で物理と数学がわりと好きだったので参加してみることにしました。すると驚きました。この中部大学でのキャンプではまず電磁波と光についての講義を受けるのですが、そこで高校で習った知識を応用して複雑な光の世界を詳しく分かりやすく説明してくれたのです。僕はこれによりこのキャンプにいっきに引きこまれました。続く実験でもいくつかは教科書の端に載っていたものもありましたが、しかしやってみると大変おもしろく、光の干渉実験では蛍光灯で作られた虹のような光に感激し、ヘルツの実験では遠く離れた発光ダイオードをつける装置をつくり、成功したときには皆がそれぞれ飛び上がって喜びました。その後レーザーについての講義を聞き、そして大学のレーザー実験室を見学しました。そこでキャンプの講師で、レーザーの研究をしている教授の先生が自分の研究の姿勢について話をしてくれました。そのときの言葉、「世界で誰も知らないことを研究するのは本当に面白い」が今でも印象に残っています。
このキャンプを通して感じること、それは「どんな勉強でも科学の道につながっていて、その先はどこまでも未来へとつづいている」ということです。僕が今まで無駄だと思っていた学校の勉強もどこかで最先端の科学につながっていることにようやく気付きました。そして研究するということはその道を一歩でも遠くへ切り開こうとする行為であることを教授の先生の態度に教えられました。今回のキャンプで僕はたくさんの人と出会いました。中には研究者でないものを目指す人もいます。それでも僕達は科学の道でつながっています。これからも交流していこうと思っています。
化学による出会い(滋賀県・高校2年生)
高分子って何?〜プラスチックからタンパク質まで〜
大阪工業大学 工学部 応用化学科
私は、このサイエンスキャンプに参加して、再び化学実験に対する楽しさ、おもしろさを実感できたことと、私と同じように化学が好きだという全国から来た仲間と共に、同じ実験を体感し、交流できたことが非常にうれしかったです。私は、今回のサイエンスキャンプでは、高分子について学んだのですが、改めて化学の不思議に興奮しました。
その気分を引き出したのは、プラスチック作成の実験でした。私は、仕上がりがうまくいくと透明で綺麗な結晶ができるという、懸濁重合というものでプラスチックを作りました。そして、プラスチックの種類の中でも食器やプラモデルに使用されている「ポリスチレン」を作りました。作成中は、温度調整と反応の変化を見て、チェックするため、長時間の観察が必要でした。そのため、目や腰が痛くなってきたり、長時間機械を使用していたため、機械の故障も何度かありました。結構“えらかった"です。
しかし、観察の中で起きた化学反応は、その疲れを何度も吹きとばしてくれました。特に、すごかったのは、溶液中に数多くの結晶のつぶができたときは、感動ものでした。いきなり無色透明な溶液中に一つの溶液を混ぜたら、いっきに結晶ができてフラスコ内が結晶でうめつくされていったからです。その反応を見たとき、私は思わず叫んでしまいました。叫ばずにはいられませんでした。そのあとにも、何回も叫んだんですが、一番印象的だったものがさきほどの反応でした。
そして、そんな私の反応と同じような反応をしていた仲間が、私の反応をより一層高めてくれたのだともそのとき思いました。今回のサイエンスキャンプに参加し、自分のいまだ知らないものと、それを一緒に知ろうと同じ気持ちで来た仲間との新しい出会いは、最高に素晴らしいものでした。
この企画に、また次の機会があれば参加したいです。
新エネルギーの研究・実験と他県との交流(広島県・高校2年生)
エネルギーを化学する〜化学が支える先端エネルギー〜
関西大学 工学部
私は今回のサイエンスキャンプを受けて新エネルギーへの発展・最先端技術の応用・色々な人との交流について学ぶことができたのではないかと思います。
一番興味を持った「色素増感太陽電池の作製」は自分で簡単に作れるように道具が一人一人配られ製作できるようになっていました。サイエンスキャンプに来る前から一度花力発電を製作して見たいと思っていました。
私が通っている高校の授業の一部では自分のやりたい研究、実験をやりまとめて発表するという授業があります。私はこの授業で花力発電のプロジェクトをしてみたいと思ったのですが、導電性物質がついているガラスが無いということで私のやりたいプロジェクトが出来なくなってしまいました。なので今回この実験ができたので良かったです。今回の色素はブルーベリージュースだったのは驚きました。私の学校では花の色素を使うと言われていたので全く予想のつかないものでした。実際にやって見たら本当に発電してモーターも回り少し感動しました。
2日目に行われた割りばしやポリエチレンからオイルを取り出すという実験も興味深いもので酸素のない所で燃やすと本当にオイルが取り出せて驚きました。また、アルミ缶でも電気を起すことができ私の知らないことがたくさんあり勉強になりました。これからの進路について多いに活用していきたいと思います。
その他にも色々な所から来た生徒達と話し合いその地域独特の話し方も面白かったです。私は手品が得意だったので皆に見せ楽しみました。昔からおとなしい性格の自分だったのですが手品への興味とサイエンスキャンプの巡り合わせが、ずいぶんと勇気づけられたような気がします。人を楽しませることが好きな私にとって大変うれしかったです。
このような充実した学習はとても身につくのでこれからも参加していきたいと思います。
目指す職業につながるスポーツ科学の今(岩手県・高校2年生)
スポーツ科学の最前線〜From Gene to Gold〜
国立大学法人 鹿屋体育大学 体育学部
私が、サイエンスキャンプに参加するのは今回が初めてです。そのため会場である鹿児島までの行き方や準備で大忙しでした。キャンプ当日まで期待半分、不安半分で夜も寝れずドキドキしていました。しかし、そんな不安はすぐになくなってしまいました。
鹿屋体育大学に到着して、参加者のみんなに会うことができました。最初は緊張で話すのが恥かしかったけど、すぐに仲良くなれました。初日ということで、まずは「スポーツ科学」について学びました。この講義では、高校の生物で習ったことも出てきて理解することができました。中には、まだ習っていないことや難しいこともあったけど、大学の先生方が私達に分かりやすく理解してもらえるように、とても丁寧に詳しく教えてくださいました。
2日目は、「三次元分析」と「筋力」について学びました。「三次元分析」では、ハイスピードカメラやモーションキャプチャーを用いて動作の撮影や分析を行いました。この実験から、ふだん私達がなにげなくしている動作を細かく分析することができました。また世界でも数少ない低圧流水プールで泳ぐことができてよかったです。
3日目は、「持久力」について学びました。まずは、最大酸素摂取量を調べる実験をしました。計算をするには大変で難しかったけど、酸素の取り込みの様子を観察でき、呼吸や循環機能の役割を理解することができました。運動やトレーニングは、トップアスリートだけでなく、健康づくりや病気になりにくい身体にするためにあることを学びました。
今回、サイエンスキャンプに参加し、たくさんのことを学び、仲間と出会えたことを嬉しく思います。学んだことは私の将来の職業に生かせることばかりです。以前よりも、より関心をもったスポーツ科学についてこれからも学習を深めていき、将来の職業を目指して頑張っていきたいと思います。
研究者の意欲の高さに触れて(神奈川県・高校2年生)
実体験を通じて海洋を学ぼう
独立行政法人 海洋研究開発機構
自分はこのような企画に参加するのが本当に初めてで不安もあったため、友達を誘って参加しました。到着すると、本当にみんな色々な所から来ていて驚きました。
最初の講義は「深海底の捜索」でしたが、約6,000平方キロメートルの海底からHⅡロケットの散らばった部品を探し出し回収するのはとても無謀だと思ったし、でも、わずか3ヶ月の間に発見・回収できたのはすごいことだと思いました。次に実習の「水中ロボットによる海底観察」では、汚い海にも意外と様々な生物がいることが分かり、また方言も交えながら色々話せたのでよかったです。
2日目の講義の「海底探査機の開発」は、興味があったので有意義に聞くことができました。自律航行が可能な「うらしま」を作る時、電波が水中に届かないためGPSが使えず、位置が分からないので、その解決策として、自分が進んだ時間と加速度を検出して位置を求める慣性航法装置の性能を向上させた物を開発したと聞き、研究者の意欲の高さや1つのロボットを作ることの大変さを知りました。そして、実習のメインイベントとも言える体験潜水では、最初は色々不安でしたが、シュノーケルの使い方から、空気ボンベを使っての注意点や泳ぎ方まで丁寧に教えてもらえ、簡単に潜ることができました。本当に、宇宙遊泳しているような感じで、機会があったら何度でもやろうと思った程でした。
今回このキャンプに応募したのは、機械の開発、特に海底を4,000メートル以上も掘り下げることのできる「ちきゅう」の造船過程などを知りたかったからでした。しかし、この企画は、海に関すること、生物環境、地震などほとんどの分野が取り上げられていたため、様々なことに興味を持つことができ、とても勉強になりました。また、違う地域に住む人達と知り合うこともできたので、またチャンスがあれば参加したいと思いました。
積極性の大切さを学んだ3日間(愛媛県・高校2年生)
意外と身近な放射線とナトリウム
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 国際原子力情報・研修センター
私の住む愛媛県では最近、伊方原子力発電所のプルサーマル計画という言葉をよく耳にします。エネルギー問題が深刻な今、原子力発電が主流になっていくのだろうか、でも原子力発電て何か危なそうというイメージがありました。そんな中、このプログラムを見つけ、参加する決心をしました。
このプログラムに参加して、私はとても貴重な体験をすることができました。1つ目は、普段入ることができない原子力発電所の施設内を見学できたことです。原子炉は止まっているとはいえ、3つもの守衛所をくぐり、中央制御室を見たりしたことなどは今でも鮮明に覚えています。2日目にシミュレータを使って高速増殖炉もんじゅを動かしましたが、そこでの操作は人間とコンピュータの意思が合致した時のみ操作できるという、お互いを監視しながら操作するという方法に感心しました。
2つ目は、放射線がごく身近なものであると分かったことです。自然放射線というものがあるということは知っていましたが、まさか衣類からもかなりの放射線が出ているとは知らず、ガイガーカウンターでブザーが鳴ったのには驚きました。
3つ目は、このキャンプで同じ志・興味を持った人たちと知りあい、仲良くなれたことです。私のように曖昧な気持ちで参加したのではなく、将来放射線技師になりたいとの夢を持つ人ばかりで3日間共に過ごし、ディスカッションしたのがとても良い思い出になっています。
今回私はこのキャンプで、何事にも積極性が大切なのだと学びました。また、より科学技術に対する興味がわき、学ぶ意欲がかきたてられました。たった3日間ではありましたが、私はこのキャンプに参加して大きく成長した気がします。3日間共に学んだ皆さん、講師の方々、そして関係者の方々、本当にありがとうございました。
理想とする自分を目指して(静岡県・高校2年生)
アミノ酸を知ろう!味の科学〜昆布からグルタミン酸の抽出・分析&味の体感〜
味の素株式会社 ライフサイエンス研究所
宿舎についてまず一安心したことがなぜかとても印象深く記憶に残っています。緊張することはあっても心配することは何もなかったからのように思います。みんな日本全国の様々な地方から来ていたので、少し自分が生活しているのとは違った感覚を持っていると思っていましたが、全然変わりなかったのが驚きでした。高校での生活だと、高校生の間での派閥や人付き合いでの利害関係などがあって、少々息苦しいものがありますが、そういったことが全く関係の無い環境というものはこんなにも良いものなのかと思いました。
研究開発職について感じたことは、まず周りの人との協調性が本当に大切な仕事だということです。ただ単に定期試験の点数が良いだけではやはりダメなんだと良く分かりました。だから味の素ライフサイエンス研究所の研究員の方々は、人間的にとてもバランスがすばらしい方々ばかりなのだと思いました。また、自分達、外来の人間に公開できる分析機器でもすごいものばかりで、どれもその機器を実際使用している研究員でないと使用法や原理を理解していないことが多いことに驚きました。本当に現代化学というものは「細分化」と「専門化」が進んでいるのだと思いました。そこで研究員の方に特化した専門分野を持っていれば研究職ができるかどうか聞いたところ、やはりカバーできる領域がある程度ないと難しいと教えていただきました。そして、研究職に就いてからも日々の勉強で領域を広め深めることが大切だということも教えていただきました。またよく考えながら会話をしていくことが大切だということを感じました。
このキャンプを通して、自分の理想とする自分へはまだまだ遠いと感じ、これからがんばっていこうと思いました。普段、自分が生活する世界とは違った世界を体験して、自分の生きる世界を変えようと思います。
交流から生まれる新しい発見(神奈川県・高校1年生)
センサが変える未来の社会!
オムロン株式会社 京阪奈イノベーションセンタ
今回、スプリング・サイエンスキャンプに参加して、貴重な体験ができた。新しい分野の知識を得ることのおもしろさ、検証することのおもしろさを知った。また仲間と協力し、意見を交わし合うことの意義もわかった気がする。
キャンプではまず光学の基礎について実習を行い、光の性質について理解した。次に、応用例として薄膜の厚さ測定を行い、想像もつかないような薄さを計測するという経験をした。最も面白かったのは、最終日の顔認識についての実習だった。かねてからセキュリティ対策について関心があり、顔認識システムには特に興味があった。「OKAO Vision」を利用し、ウェブカメラを使ってパソコンに顔を取り込み、自分の顔を認識させた。この実習で、性別・国籍を判断するポイントや、顔認識の難しさなど、いろいろなことを考えさせられた。実習を通して、基礎的な知識はしっかり理解しなくてはならないこと、もっと知りたいと思うことの大切さがわかった。そこから自由で現実的な発想や疑問が生まれてくるのではないか。
また、同じキャンプの参加者達と驚くほど早く打ち解けて会話を交わせるようになり、いろいろな人の新しい意見や発想に感心したりして、自分にとって大変刺激になった。新しい発想は人との交流の中から生まれてくるものではないかと気づかされた。センターの施設内に、大部屋方式のオフィスや、気軽に議論できるコミュニケーションスペースが設けられているのも、技術者・研究者の間でコミュニケーションが取りやすい環境になっているのだろう。
知識を広げることはもちろんのこと、人間的にももっと幅を広げていくことが大事だと気づかされた有意義なキャンプであった。
研究者に触れ、将来の夢が膨らんだ(東京都・高校1年生)
超高層ビルの世界へようこそ
鹿島建設株式会社 技術研究所
鹿島建設のプログラムは主に液状化とビル風についてでした。液状化は水そうに砂と水を入れよく混ぜて水で飽和させた土壌をつくります。そこにピンポン玉・アルミ・鉄・コーヒー缶を埋め込みそれぞれ揺らし、出てくるかこないかを実験しました。出てくるもの、出てこないもの半分出るものと様々でしたが、それらはすべて比重の関係で説明されました。
ビル風では人が立っていられないような風速25メートルの風を体験し、風の恐ろしさを実感しました。その風を、木を使って和らげる方法を研究者の方の指導で実験し、ビル風の対策に街路樹が大きな役割をしていることを知り、驚きました。他にも、コンクリート・超高層ビルの基礎講座、屋上緑化、耐震・免震の施設見学など盛り沢山でとても有意義で楽しいものでした。
建築は建物を作るイメージしかなかったのですが、屋上緑化では屋上に負担をかけない軽く、養分豊富な土を研究したり、病気での磁気を使った治療で、患者さんへの圧迫感を失くす透明な磁気のもれない壁を開発したりと実に様々な分野があるのに驚きました。また屋上緑化など、環境のことを第一に考える仕事が今求められていると感じました。学校で習った物理の知識が私達の生活の身近なものに利用されているのにも驚きました。
キャンプでは研究者の方々との懇親会もありました。研究者の方がどうしてこの仕事を選んだか、大学で何を勉強したか、今会社でどのようなことをしているかなどをお話して下さり、質問にも丁寧に答えて下さいました。研究テーマの多さや会社の組織などが分かり将来の夢が具体的にイメージできました。
引率の方々の細かい気配りのお陰で皆とすぐうちとけることが出来ました。また、同じ事に興味をもつ人達が集まったので将来の話など共通することも多く良い刺激になり夢もまたふくらみました。春休みの思い出になり、新たな目標も見つけることが出来ました。
風の強さを魅た感じた(静岡県・高校1年生)
風の強さを魅る感じる
清水建設株式会社 技術研究所
『パーシャルフロート』これは、今回私が参加したスプリング・サイエンスキャンプの会場である、清水建設株式会社技術研究所の風洞実験棟の建築方法である。なんと建物の半分が地下部分のプールに貯められた水の浮力によって支えられ、残りの重量は積層ゴムと呼ばれる柱によって支えられているという、地震に強い建物なのだ。地震の細かく速い揺れを水と積層ゴムの力でゆったりとした揺れに換えることがこの風洞実験棟のポイントである――と会場についてから説明を受けた。
私は実際に体験できないとなかなか納得できない。だからこのように聞いた時は、頭では理解しながらもどこかでこの建物が水に支えられているわけがないと疑っていた。しかし、施設見学で水が貯められているのを見て、お世辞ではなく心から「すごい」と思った。私だったら絶対に水の中に建物を入れて免震しようなんて思いつかないだろう。驚きだった。
パーシャルフロートはサイエンスキャンプで印象深かったものの1つだが、もう1つはやはりなんといっても実験だ。ここでは、テーマである「風の強さを魅る感じる」ために、ブロックで40cm以上の建物を建て、風を当てる。そしてどれだけ風の影響を受けにくい建て方をするかが課題であった。
私のいた班では全部で5種類建て、結局最後に作ったものが一番良い結果となった。それは建物に当たった風によって作られる渦を打ち消すように工夫したことによるものだ。実験を重ねてどう工夫したらよいのか考え、ドキドキしながら結果を待つことは本当に楽しく良い経験となった。まさに「風の強さを魅た感じた」といえるだろう。
また今回のサイエンスキャンプで、普段の生活では決して交流のない友人が全国にでき、進路について考える上でもとても良い刺激となった。もしこのようなすばらしい機会があったら、ぜひ積極的にチャレンジしていきたい。準備して下さった清水建設、事務局の方々、本当にありがとうございました。
直接見聞きして学んだ科学的な考え方(東京都・高校3年生)
資源・エネルギーと環境保全について考える
東京電力株式会社 技術開発センター
今回のサイエンスキャンプに参加しようと思ったのは、地球温暖化に対して、大量の二酸化炭素を出しやすい発電所を扱っている東京電力がどのような対策をとっているのか、とっていこうとしているのかを直接見聞きし、それを自分の将来に役立てていきたいと思ったからです。
講義では京都議定書で決められた基準でさえ、現状ではまだまだ甘いということを知り、今の自分達に何ができるか深く考えさせられました。バイオマスでは一例として、柑橘類に含まれている油成分を抽出する実験を行いました。実験では外部加熱と内部加熱、20ミリと5ミリの2つの皮の大きさを使う4種類の実験をしました。内部加熱は大きくすると均等に過熱することが難しいのでまだ実用段階ではないというのを聞いて、どんなに効率が良くても、なかなかうまくいかないものだということを知りました。金属では、実際に発電所で使われていたタービンなどの金属材料がどこまで耐えられるのか実際に壊してみたり、表面を腐食させてみたり、走査型顕微鏡使って金属の状態を直接見て調べたりしました。これらの実験で私は、科学的な考え方や実験で得られた情報をどのように使っていくかを学びました。研究施設ではリチウム電池で走る自動車に乗せてもらいました。自動車はとても静かで、走り出しもとても滑らかでした。しかし、充電に時間がかかりすぎてしまうこと、「発進時の音がないためにそれが他人を危険な目にあわせてしまう可能性がある」ということを聞いて、そういうところにも気をつけなければいけないんだと気付きました。
今回のサイエンスキャンプに参加して、地球温暖化を防止するための仕事に就きたいと強く思いました。3日間ずっと私たちをサポートし、様々な質問に丁寧に分かりやすく説明してくださり真にありがとうございました。
ナノに触れて(茨城県・高校1年生)
ナノメートルの世界を観る〜ようこそ「電子で観るナノメートルの世界」へ〜
日本電子株式会社 本社・昭島製作所
ナノの世界を見る。それを聞いた時私はまったく実感が湧かなかった。ナノ=10億分の1と言われてもあまりに小さな数で、何より肉眼で到底見ることの出来ないものを見るというのは私にとって想像を超えたものであり、そんなものを見るのは大学の教授とか研究者の人などで、一般人でしかも高校生である私には興味はあるもののまったく関係のないものだと思っていた。
しかし研究所へ行きそれを実際に見せて頂いた時には本当に感動した。最初に見せて頂いたのは講義の中で研究者の方が顕微鏡で撮った物だったが、大きな物をどんどん拡大してゆき、細かな凸凹、さらには原子の並びまで見えた時には、本当にこの世界は原子で構成されているんだと今更ながらに感心をしたと同時に、この機械を作るのに相当な研究者の方々の知恵と努力がかかっているのだろうなと思い、本当に研究者の方々は素晴らしいと思った。また最先端の電子顕微鏡に触れ、原理こそは理解しきれなかったけれど、ナノの世界と顕微鏡の操作の簡単さに驚き、自分の身の回りに見えない所でこんな光景が広がっていると思うと、この世界は素晴らしいと思った。
みんなとの会話の中では、今まで自分の知識の浅はかさと視野の狭さを感じ、何事も広く取り組み、考えていかないといけないと思った。このサイエンスキャンプで同じ興味を持った仲間、研究者の方々と出会え、これからの自分について考えさせられたり自分は全然駄目だなと思ったりと考え方が大きく変わり、この経験で将来が大きく左右するだろうと思う。今考えると、実験中は技術が凄過ぎて何がなんだか分からなくて質問があまり出来なかったのが残念だけれど、サイエンスキャンプに参加出来て本当によかった。そしてこのような経験をさせて頂いた研究者の方々には心からお礼を言いたい。
情報技術に触れて(神奈川県・高校1年生)
安心・安全・楽しい未来を実現する情報通信技術を体験しよう!
日本電信電話株式会社 横須賀研究開発センタ
今回のサイエンスキャンプは、自分が進みたいと思っている方面とは違うのですが、光ファイバーというものに興味を持っていたため、参加しました。始めはNTTが開発したものの見学でした。センサーや映像、音を使って見る者を楽しませてくれるものが展示されていて、これからの情報通信の技術を感じたと同時に興味も広げることができましたし、何よりNTTに親近感を持つようになりました。
1つ目の講義は暗号についてでした。習っていない数学の知識や大学レベルの内容の講義で、正直全くと言っていいほど理解することはできませんでした。しかし、暗号の基本的な考え方と研究者の方々の熱心さはとても伝わってきました。また、数学をきっちりやってから聞きたい内容でした。
2つ目の講義は、映像コンテンツの制作、実習でした。動画から一部を切り取り、マウスで動く部分に触れると自分で画像を動かすことができるというユニークなものでした。とっても簡単にアイデア次第で面白い物を作ることができました。私達はその時の持ち物でこれを作ることになったので、私は友達と考えて、傘を振り回す画像を作りました。最後に開発者の方が、「あなた達に今あるもので作ってもらったのは、研究者というものは数少ないものの中で発想して作るということが大切だからです」と言われ、私はこの言葉が深く残りました。
立食パーティでも、思っていた以上にNTTの方とお話できて、見学で見たものを私たち高校生から感じた意見を交換することができました。
光ファイバーでは、中を顕微鏡で観察したり、種類による使い方の違い、研究室をのぞかせてもらいました。今まで疑問に思っていた光ファイバーのことも丁寧に解説して下さり、とても満足のいく内容でした。
ありがとうございました。
機械について楽しく学べた3日間(福岡県・高校2年生)
身近な機械を覗いてみよう
株式会社日立製作所 機械研究所
サイエンスキャンプに参加して様々な身近にある機械について知ることができました。普段使っているATMの実習でも見ることが出来ない中の構造が見ることができ、それを詳しく教えてくれ、さらに自分達で装置を使って紙幣が重ならないわけ、飛び出さないわけを様々な機材を使って実験をして記録していき調べました。
次の実習は、ハードディスクの中を実際に分解したり、高速度カメラを使って落下実験を行ないました。小さく壊れやすい装置で中を見たときも、本当に精密でこのようなものがどうして大量の情報を記録できるのかと思いました。でも、講師の方がわかりやすく説明してくれて少しは理解できました。落下実験の時は、友達と知恵を出し合って落ちても壊れないように工夫しました。1回目より2回目の方が少しは衝撃を抑えることができました。その日の懇親会で研究所の方に様々な質問ができ、とても参考になって良かったです。最終日は、「風の音を聞いてみよう!」というテーマで、まず無響室に入り全く音が反射しなくて不思議に思いました。部屋の壁が特殊で吸音材というものを使っているそうです。そこで自分の声を聞いたり、装置を使って知ることができてとても楽しく学べました。
次の低騒音風洞を使って鉄道のパンタグラフの出す騒音について調べました。将来鉄道関係に就きたいと考えているのでいい参考になりました。空気の流れをパソコンとグラフ化したのを見たりして、秒速と周波数のピーク時は比例しているとわかりました。
最後は、おもちゃについての実習でした。いくつかのコマや他のおもちゃの動きをシミュレーションしていてとても興味を持ちました。おもちゃにもたくさんの力学が使われているのを当たり前だけど、それを詳しく分かり易く教えてくれました。そして、コマのお土産をもらいました。
短期間でしたが、多くのことを学べました。友達もできて3日間楽しく学習できました。
海外とのリアルタイムな交流(広島県・高校2年生)
ハイブリットコミュニケーション〜先端技術で未来メディアの研究プロセスを体験しよう〜
【伝えたい☆〜もっと、もっと!コミュニケーション】
富士ゼロックス株式会社 研究本部
高校では放送部に入り、コミュニケーションに関心があった私にとって、この3日間はとても充実した毎日でした。そして、全国から集まった同世代のみんなと出会えたことも、かけがえのない思い出です。
富士ゼロックス研究本部では、実際に電子ペーパーや触覚マウスに触れることができ、最新技術の素晴らしさに驚きました。これらが近い将来実用化されれば、医療など様々な分野で応用されることはもちろん、紙の使用量の削減につながり、地球に優しい未来がやってくるのだと思います。遠隔コミュニケーションの実験では、ジェンガを用いて情報伝達を競い、それを観察することで、伝える難しさを学びました。その実験を基に、チームごとに発表をするのですが、まとめの段階から本当に多くの意見やアイデアが出され、とても活発な意見交換をすることができました。
中でも私が一番印象に残っているのが、海外研究者の皆さんとの遠隔会議です。日本とアメリカをつなぎ、相手の映像を見ながら、リアルタイムで交流ができたことはとても印象に残る体験でした。そして研究者の皆さんに質問することができ、英語で会話をしたことは、緊張しながらもとても楽しいものでした。また同時に、将来的にも英語は絶対に必要なんだなと感じました。
このキャンプを通して私は、広い視野で物事を考える大切さを実感しました。遠隔コミュニケーションの実験でも、話し手と受け手という2つの視点から観察することで、実験を細かく分析できるのだと分かりました。また研究者の皆さんは、文系・理系を問わず多くの分野から集まっており、これが広い視野を持つことにつながるのだなと感じました。
この3日間で多くの人にめぐり会えて、たくさんの刺激をもらうことができました。最後になりましたが、今回指導していただいた研究所の皆様に心から感謝します。本当に有難うございました。
実用化に向かう砂糖電池(埼玉県・高校1年生)
体験しよう!未来の電池の作り方
松下電器産業株式会社 先端技術研究所 ナノテクノロジー研究所
砂糖電池の実習は難しそうでついていけなかったらどうしようという不安もありましたが、組み立てや計算、考案などもすべて研究員の方々が順序立ててわかりやすく説明してくださったので不安や滞りもなく進めることが出来ました。今回使わせていただいた砂糖電池が実際に今実用化に向けての研究中であると聞いたので、商品になるとしたら一体どのような形で使われるのかということが気になりました。燃料電池の紹介の際に、生ゴミや砂糖をつぎ足すことで充電の必要のなくなる電池などの例が出されていたので、本格的な段階までは出来なくても自分なりに考えてみられたらいいと思います。
松下さんでは最先端技術を扱っているだけあってとても厳重なセキュリティロックがしてあったので、ICカードなど、今回の実習とは違う面でも先進技術を見せていただけたと思います。声に反応して選局、ジャンル検索をしてくれるテレビ等、音声を認識する製品は将来的にはバリアフリーの観点でとても有用なものになると思います。今回様々な最先端技術を見せていただいたことで、普段あまり考えていなかった技術面、実用面での製品に対する新しい考え方を持つことが出来ました。また、このような機会がないと知り合うことのない遠方の友達との貴重な出会いもできてとてもよかったです。
このキャンプで学んだり得たりしたものは数知れずあります。あと2年間高校に在学している間に、出来る限り何度でも応募し、また参加したいと思います。3日間、どうもありがとうございました!!
感動した、環境に対する考え方(栃木県・高校2年生)
ユビキタス時代の新しい技術を体験しよう〜撮って創っていろいろプリント〜
株式会社リコー 中央研究所
今回私がサイエンスキャンプに参加しようと思った理由は、進路を決定するにあたり研究者や技術者に対して具体的なイメージをもちたいと思ったからです。そして以前から画像処理やプリント技術に興味があったので、リコーを選びました。最初のうちは緊張して初対面の人とうまくやれるか、実習の内容についていけるかどうか不安でした。けれど他の参加者は皆とてもいい人で、すぐに打ち解けることができました。実習中も研究者の方々が分かりやすく説明してくれたり、質問にも一つ一つ丁寧に答えてくれたので実習を楽しむことができました。研究所で過ごした2日間は驚きと感動でいっぱいでした。
デジカメやコピー機など普段何気なく使っているものも内部がどのような構造になっているのか全く知らなかったので、特にコピー機の仕組みには驚きました。またリコーの最先端技術で私が最も魅力的だと思ったのはリライタブルプリントの技術でした。特殊加工をした紙に熱を利用して200回近く文字を印刷したり消したりできるこの技術は、無駄な紙を使用せず、ゴミも出さないという環境にやさしいものでした。身近な小さなことにも環境を考えた配慮があり、リコーの方々の環境に対する考え方に感動しました。そして懇親会などでの研究者の方々との会話も私に大きな影響を与えました。
リコーの研究者は皆、生き生きと自分の好きな研究を楽しんでいました。今まで研究者や技術者というと男性のイメージが強かったけれど、リコーには女性の研究者もたくさんいました。「これからはどんどん女性にもこの世界に入ってきてほしい」という本部長さんの言葉を聞いて、私は自分の進路に自信がもてるようになりました。ずっと夢を持ち続け、この経験を活かして少しずつでも自分の夢に近づけるように努力をしていきたいと思います。このような貴重な機会を与えてくださり、本当にありがとうございました。