|
2003年3月開催のスプリング・サイエンスキャンプに参加した高校生・高等専門学校生158名にアンケートの協力をお願いところ、147名から回答をいただきました。プログラムの内容とキャンプ後の科学技術分野への興味の持ち方の変化について、参加者の感想を紹介します。
サイエンスキャンプに参加してプログラムの内容については、丁度良いと感じた人が51%(75名)いました。次いで、やや難しいと感じた人が37%(55名)でした。やや易しいと感じた人は8%(12名)、かなり難しいと感じた人は2%(3名)、かなり易しいと感じた人は1%(2名)でした。サイエンスキャンプの内容は、高校生にとって丁度良いと考えられます。
プログラムの内容(難易度)(%)
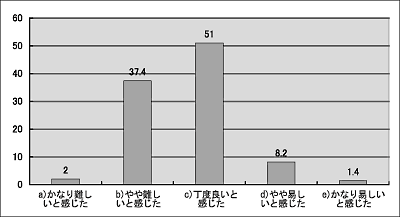
キャンプ後の科学技術分野への興味の持ち方の変化については、多い順位に上げると、科学技術分野の雑誌・本をよく見るようになった人が28%(72名)、新聞で科学技術分野の記事をよく見るようになった人が19%(51名)、テレビで科学技術分野の番組をよく見るようになった人が18%(48名)、友人と科学技術分野の話題がよく出るようになった人が14%(38名)、家族と科学技術分野の話題がよく出るようになった人が13%(34名)いました。その他には、キャンプ関係の分野への学習意欲が上がった、学校の専門系授業にさらなる興味がでてきた、キャンプでの体験をベースに様々なことを調べる癖がついた、図書館へ行き詳しく調べるようになった、アイデアを紙に書くようになったという人がいました。参加した高校生は、科学に対する親しみが一気に高まったようです。
参加後の科学技術分野への興味(%)
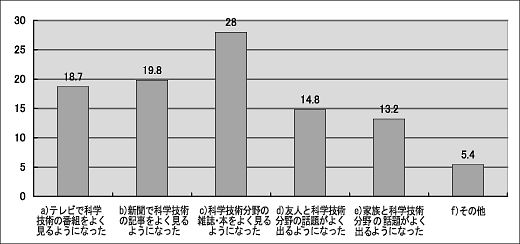
|