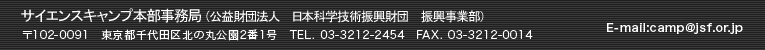「深く超伝導を知る」(岩手県・高校2年生)
量子世界の体験~超伝導を体験しよう~
国立大学法人 岡山大学大学院 自然科学研究科
私がこのプログラムに応募する際、第1希望にこれを書くべきかどうか、大変迷いました。なぜなら、会場が遠かったからです。しかし、私は超伝導について非常に興味を持っていたので応募することに決めました。
参加にあたっていくつか超伝導に関する本を読みましたが、思っていたよりも難しい内容ばかりでした。しかし、ある程度読んでいたおかげで野原実先生の講義が自然と頭に入ってきて理解することができました。絶対温度の表し方に慣れるのには少し時間がかかりましたが、今では液体窒素の77K付近ならイメージできるようになりました。また、大学生が卒業研究で世界記録の超伝導を発見した話や、鉄系の超伝導が2年だけで金属系の超電導のTcを越したという話には大変驚かされました。
2日目は液体酸素や電子顕微鏡など、見たり体験したりといったことばかりでした。最初に極低温の世界や、極小の世界を体験させていただきました。温度と気体の体積の関係について知ったり、実際に液体窒素や酸素を見て窒素が固体になることや液体の酸素が青いことを知りました。電子顕微鏡で超伝導体を見て、超伝導が実は穴ぼこであることや、電子顕微鏡でそこにどんな原子があるのか分かることを知りました。
最終日には初日に作製した超伝導体も成功してマイスナー効果や抵抗率ゼロを見ることができました。このプログラムで一番楽しかったことは研究者の方から話を聞き、直接会話ができたことです。
学校に帰り、もう1度作製したところマイスナー効果が確認されました。
現在は鉄系超伝導に挑戦してみたいと考えています。作製が成功したり鉄系という新しい視野を広げられたのは指導して下さった先生方のおかげです。今後私が課題研究を進める上で交流することがありましたらよろしくお願いします。
(今回は、サイエンスキャンプDXとして5泊6日で実施されます。)
「サイエンスキャンプでの貴重な体験」(岩手県・高校2年生)
いろいろな物質・材料に触れてみよう
独立行政法人 物資・材料研究機構
今回のサマー・サイエンスキャンプでは「いろいろな物質・材料に触れてみよう」というプログラムに参加させていただくことができました。
私は化学が好きで、材料の分野に興味があったので、夢のような3日間を過ごさせていただきました。
初日の電気抵抗や超伝導の実験では、実際に自分の目で超伝導が起こる瞬間を見ることができ、とても感動しました。
2日目は実際に試験を行い、材料の強度や靱性を調べました。シャルピー衝撃試験では、温度を変えた試験片を破壊し、破面を走査型電子顕微鏡で観察しました。金属の引張実験では、液体窒素で冷やした試験片と室温と同じ温度のものを機械で引っ張り、強度を調べました。これらの実験から、同じ素材であっても、温度を変えたり、叩いたりして少し加工すると、性質が変わってしまうことが分かりとても驚きました。
3日目の所内見学では、研究室を見学し、研究者の皆さんがどのような研究をしているのかを説明していただきました。個人的に走査トンネル顕微鏡の研究室で材料の表面の原子を見ることができ感動しました。
始めの方に、夢のような3日間を過ごさせていただいたと書きましたが、それは今回参加した他の19名の仲間のおかげです。仲間がいてくれたからこそ、試験はうまくいったし、試験から得たデータについて議論し、有意義な時間を過ごすことができました。仲間の皆さんには感謝してもしきれません。
今回のサイエンスキャンプで感じたことは、やはり、化学が好きといってもまだまだ知識が足りないなと思いました。なので、これからより一層勉強に励みたいと思います。
最後になりますが、引率の先生や施設の方々には3日間本当にお世話になりました。ありがとうございます。
「薬の生成を通して学んだこと」(香川県・高校2年生)
くすりを「知る」・「創る」・「活かす」
関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学三大学医工薬連環科学教育研究機構
今回は薬がどのように医学・工学・薬学と関わっているのか知りたくて参加しました。
一日目の消化薬の働きについての実験の内容は難しかったですが、時間を正しく守り測定するという実験の初歩的ですが、大変重要だということに気付きました。初めて見る機器を触って実験できて良い経験になりました。そして難しい内容でも、先生の話をよく聞くと理解できたので良かったです。
二日目は薬用植物園をまわり、匂いを嗅いだり食べたりすることで、「こんな植物からあの薬ができるのか!」と実感がわきました。顕微鏡で血液や腸の柔毛、大腸菌やブドウ糖の観察もしました。私は一番血液の中について興味を持ちました。赤血球、白血球はもちろん、好中球、好酸球、好塩基球等学校の実験では見せてもらえないものが見ることができたので嬉しかったです。その後は、製剤作りをしました。薬の効能や体の部位に合わせて、さまざまな形の剤形があり、薬を作るのは薬の中身だけでなく形までもよく考えなければならないのだと分かりました。錠剤とカプセル剤を作ることで薬が粉の状態から粒になるまでがよく分かりました。
三日目に薬剤師の方から薬を扱うことについての話を聞きました。同じ効能の薬でもさまざまな形に加工することで多くの人に使用できるようにするということを聞いて新しい薬を作るだけでなく改良することの大切さを学びました。
三日間初めて聞く言葉ばかりでとまどいましたが、難しい内容でも知りたい!分かりたい!と一生懸命話を聞いたり積極的に活動することによって理解できたときは、本当に嬉しかったです。同じような志を持った仲間と討論することにより意見を交換しあえるのはとても新鮮で新たな考え方を知れてよかったです。このキャンプを通して、薬について知れて、自分の夢に向かって頑張ろうとより一層強く思うようになりました!
(今回は、サイエンスキャンプDXとして3泊4日で実施されます。)
「目に見えない線虫でつながっている東京と盛岡」(東京都・高校2年生)
松を枯らす線虫をDNAで検出しよう
独立行政法人 森林総合研究所 東北支所
「全国からDNAに興味を持った8人の高校生が集まる」。私は参加する前、自分はついていけるのか不安で、生物の先生に線虫についての質問を沢山していました。そして、ついにキャンプ初日。講義を聞いていくうちに私の中の不安は消え、日本の松についてあまり興味をもっていなかった私は、いつの間にか興味と講義内容への質問をもち始めていたのです。その日、研究員の方は「方法が大切」としきりに言っていましたが、その意味はまだよく分かりませんでした。
2日目、前日の「方法」というのがよく分かりました。方法というのは、もちろん機具の取り扱いやコンタミを防ぐことなどもありますが、しっかりと筋道の通った方法の中には新しい発見があるかもしれないということが分かりました。実体顕微鏡で、線虫の中にいた原生動物を発見できたり、線虫は頭からうねるように動いていて絡まっていたのを観察できたり、光を下から通すと体内の腸などが見えてキラキラ光り美しいと思えたり、線虫の口には針があり、それで食べ物を取っていたり…。私は初めて顕微鏡の世界に魅力を感じました。そして、まだ発見されていない沢山の種類も含めて、目には見えない線虫という動物にもそれぞれの生活があり、種によっては人間と同じように、それぞれ個性があるということを知り、感動しました。
その夜、10時過ぎまで発表準備をしていたときの「たとえ他のその実験に関する情報を知っていたとしても、自分の実験以外の余計な情報は検証していないからむやみに入れてはいけない」というアドバイスによって、班員と協力して、2日間勉強したことを凝縮した発表ができました。
たった2泊3日。しかし不安を乗り越えて実行に移した自分に今では感謝しています。最終日に先生から頂いた「アメーバ」を見る度に、私達の為に尽くしてくださった研究員の方々を思い出します。本当に、初めてだらけの良い体験をさせていただき、ありがとうございました。東京と盛岡が線虫でつながっていると思うと少し嬉しいです。
「気持ちが変わった夏」(長野県・高校3年生)
動物を衛(まも)る ヒトを衛(まも)る
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所
僕は「将来、獣医師になりたい」との思いから始まり大学のオープンキャンパスでサイエンスキャンプのことを知り参加しました。きっと難しいことをやったりすると思い、自分にできるか不安な気持ちでしたが、僕が想像していたものとは全然違うものでした。
まず、実験や実習は1人1つの物を使うことができ、講師の先生も1人ずつついてくれ、実験が苦手な僕でも理解しながら、スムーズに進めることができました。その実験の中で僕が1番興味をもったことは、解剖したマウスを使って行ったPCR実験です。1日目に生きているマウスを死なせて解剖するのも驚いたのですが、それ以上にPCR実験は僕の中では驚き興奮しました。あんな小さな肝臓の断片を使って様々なことがわかり、教科書でしかみたことがなかったDNAの二重らせん構造も肉眼でみることができ感動しました。
また、講師の先生方やほかの研究者の方々と食事会のときに話す機会があり、その中の1人が言っていた「獣医は、人以外のすべての動物をみる医者なんだよ。」という言葉が強烈に印象に残っています。僕は、祖父と父が獣医師でその仕事を間近でみていて、どんなものか勝手にわかっている気になっていたのですが、それは、獣医師の仕事の一部だったのだと気づかされました。しかし、臨床も研究もやり方は違うけれど、共通していることは、両方とも人や動物のためにしているということは同じだと思いました。
将来僕は、大学に入って大学院まで進んで研究をして、それから地元に帰りそれを生かした臨床の獣医師になりたいです。このキャンプを通してただ獣医師になりたいと思っていただけでしたが、どんな獣医師になりたいという明確なイメージを作ることができました。
キャンプの為に準備をしてくださった講師の先生方、事務局の方々お忙しいなか感謝しています。本当にありがとうございました。
「貴重な体験」(大分県・高校1年生)
生物が見る世界~いくつもの目といくつもの世界~
国立大学法人 浜松医科大学 医学部
私はこのサマー・サイエンスキャンプで、多くのことを学び、貴重な体験をさせていただきました。このキャンプで最も感じたことは、科学はとてもおもしろいということです。私は、このキャンプ中ずっと、科学が楽しくてたまりませんでした。このキャンプで私は科学がいままで以上に好きになりました。
次に、大学はとても楽しい所だということです。今回、私が参加させていただいた浜松医科大学には、多くの優しい先輩や、おもしろい先生方がいました。私は「こんな方々と毎日、研究や実験ができるなんて楽しいだろうな。」と思いました。
このキャンプの中で体験させていただいたカエルの解剖はとても貴重な体験の1つです。初めは気が引けましたが、最後まですることができました。
そして、レポートの作成も貴重な体験の1つです。いままでレポートを書いたことのなかった私にとっては、とても難しいことでした。ですが、わからないところは先輩に聞いたり、仲間と話し合ったりして作成することができました。
このキャンプでは多くの仲間ができました。初めは、仲良くできるか不安でしたが、自ら話しかけてみると、すぐに仲良くなることができました。
私はこのキャンプでできた仲間とこれからも仲良くしていきたいと思っています。
私はこのキャンプに参加できてとても良かったと思っています。このキャンプを紹介してくれた学校の先生にはとても感謝しています。このキャンプで同じ志を持った人達と触れ合うことによって、これから自分も頑張っていかないといけないと思いました。もし、次、このような体験ができるプログラムがあれば積極的に参加したいと思います。
今回はこのような大変素晴らしいプログラムを組んでいただき、本当にありがとうございました。
「有意義な3日間」(岩手県・高校2年生)
理研の最新研究成果を体験しよう!!
独立行政法人 理化学研究所
私は生物が大好きで、将来医療系の職に就きたいということもあり、今回「化合物を使って病気の原因をサイエンスしよう」というテーマに惹かれこのコースへの応募を決意しました。
応募するにあたって、理化学研究所について調べていく中で、沢山の実績をあげていることを知り、以前にも増して参加への意欲が高まりました。
このコースでは大きく3つの実験を体験させていただきました。どの実験も初めての体験で大変貴重な時間を過ごさせていただきましたが、その中でも鶏卵を用いた血管新生の測定の実験が印象に残りました。これは、ガンの血管新生を抑えることに応用しようというものだとお聞きして、近い将来今以上にこの治療法が身近になるのかと考えると、大変感動しました。
実験そのものは、一つ一つの動作がそれも初体験で、とまどいもありましたが、実験結果を自分の目でしっかりと確かめることができたときは嬉しかったです。
そして何より今回のサイエンスキャンプで多くの研究者と出会ったこと、同じ夢を持った仲間と3日間共に過ごしたということが私にとって大きな刺激となりました。私が主にお世話になった研究室の方々は、どの方も熱心に私達高校生にも分かるよう丁寧にお話してくれました。また、気さくな方ばかりで、とても良い雰囲気の中で体験させていただきました。予想以上に女性の研究者の方が多く、カッコいいなと思ったし、憧れの存在となりました。3日間共に過ごした仲間とは普段の友人との会話とはまた違って新しい世界が広がった気がしました。
3日間普段はできない体験を沢山させていただき、驚きと感動の連続でした。自分自身の視野も非常に広くなったように思いますし、これからずっと付き合っていける友人も出来ました。3日間でお世話になった全ての方に感謝しています。
(今回はプログラム、実習内容が異なります。)
「自然災害発生のメカニズムを学んで」(京都府・高校1年生)
自然災害が発生するメカニズムを学ぼう
独立行政法人 防災科学技術研究所
僕は、中学生の時に地震の研究をしていて、将来地震の研究等の仕事に就きたいと考えていました。なぜなら、母が阪神・淡路大震災の時、僕を妊娠中に被災して、その苦労話を聞かされ、1人でも多くの人を地震から守りたいという気持ちがあったからです。
これが今回サマー・サイエンスキャンプ2010に参加した理由です。3日間という長い時間でしたが、とても良い経験をすることができました。本来見ることのできない防災科学技術研究所は、思ったより広く、最新の実験施設が揃っていてとてもびっくりしました。また、先生方の熱意のこもった講義も印象的でした。僕はその中でも2つの講義が印象に残っています。
1つ目は、「火山が噴火する仕組み」です。これまで地震の研究しかやってこなかった中で、火山の講義はとても刺激的でした。火山は時には重大な被害を及ぼすことがあっても、観光資源や地熱発電など、僕たちの生活に深く関わっているということを改めて講義を通じて知りました。
2つ目は、「Dr.ナダレンジャーの自然災害実験教室」です。雪崩や液状化現象や固有振動など、様々な自然災害を玩具にしてしまうという少し変わった考え方で、とても面白かったです。自分に危険が及ばない災害は、人間は笑ってごまかしてしまうということで、ちょっと複雑な気もしたのですが、災害を簡略化することで、理解しやすくなったなぁと思いました。
このように、今まで勉強してきた地震もさることながら、今までほとんど知らなかったり興味が無かった火山や雪氷災害にも触れ、自分の将来にも関わる良い経験をすることができました。今後も地震などの自然災害についてもっと深く勉強したいと思っていますが、この経験を忘れず、これからの将来に活かしていきたいです。
「通過地点」(神奈川県・高校1年生)
あなたも体験 未来のロケット技術
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 角田宇宙センター
ロケットといえば、私のこれまでの人生とは程遠いものがあった。本物なんてもちろん見たことはないし、せいぜいペットボトルロケットを先輩方がとばしているのを見たという程度だ。
私は、エネルギーに興味がある。原子力発電だとか、風力発電、太陽光発電だとか、何もない別々のところから新たな「何か」が生まれる原因の、エネルギーが発生する…そこに神秘とロマンを見出していた。
このサマー・サイエンスキャンプを終えて私は変わった。今までのエネルギー好きからロケットのエネルギー好きへと変化した。
ロケットの中。それは限りの中で莫大なエネルギーを生み出すことが必要とされる世界である。いかに効率よくターボポンプを回すのか、どうすれば更に重さを減らすことができるのか…(ラムジェットエンジン)。設備見学や講義は、ロケットが最先端技術の結晶である証のように思えた。
来年から私は専門科目を学び、再来年には課題研究をすることになる。
ここで学んだ技術をより深く、より身近に生かすことができるように勉強していきたい。
最後になってしまったが、私がこのキャンプで痛感したことがある。それは一般科目の必要性だ。特に英語。海外の実験器具ならば 取扱説明書も英語を始めとしているだろうし、こういう研究は日本国内だけでなんとかなるものではない。だから世界共通語の英語は大切だと感じた。
専門知識のみでなく、こうしたことも教えてくれたこのサマー・サイエンスキャンプには本当に感謝したい。様々なことを学んだ3日間。この3日間は私の人生における、大切な通過地点だったのかもしれない。
「化学と科学技術の交わり」(栃木県・高校3年生)
原子力研究における最先端技術を体験してみよう!
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター
私は、化学が大好きで、化学の様々な元素の性質をどのように使ってエネルギーにしているのかについて知りたくて応募した。だから、原子力についてはほとんど知識がなかった。しかし、やはり原子力も化学の応用であるため、ナトリウムやウラン、ヘリウム、プルトニウムなどの元素の反応や性質を使って成り立っていた。研究所の人達は工学部の人が多かったが、地球温暖化を防止するために、CO2を出さないように、そしてより効率よくエネルギーを使おうと、元素の性質について知りつくしていた。実験を追及し、成功することに全力をそそいでいる姿は研究者そのものであり、とても憧れた。
そして、同世代の人たちと話していると、私より、どの分野においても知識が長けていてとても刺激を受けた。だから、もっと化学について知識を身に付けて、現代の最先端技術についても、どのように化学が活かされているかについて興味を持とうと思ったと同時に、自分の勉強不足を身にしみて、日本全体からの自分の知識力を客観的に見ることができた。やっと受験生なのだと自覚した。
今回のサイエンスキャンプは、とても貴重だったと思う。10人全員が仲良くなれ、それぞれの意見や考えを聞いて、自分の知識へと蓄えることもできた。それから、化学式でしか見たことがなかった反応を直接見ることもできた。やっぱり化学こそが1番面白くて、興味深い教科だと再認識できた。
私は、科学者・研究者となるために一心不乱に頑張れる自信をつけたし、科学者・研究者になってから、どのような研究をしたいかの目標も定まった。この心構えを身に付けることができたのも、このサイエンスキャンプのおかげである。本当に、ありがとうございました。
「サマー・サイエンスキャンプを通して」(京都府・高校1年生)
不思議な世界をのぞいてみよう!~最先端の地下研究~
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 幌延深地層研究センター
私は、最初このサマー・サイエンスキャンプに参加するまでは地層処分のことについてはあまり知りませんでした。どんなことがどんな所で研究されているのか分からなかったので、今回参加して、よく知ることができました。特に私は、弾性波トモグラフィの方法を知ってとても驚きました。
波を発生させて受振機でそれをキャッチするだけで内部の物が分かるというのがすごいと思いました。それをするには、各物質を通る波の速さを調べないといけないということが分かりました。
また、同じようなことに興味を持つ、全国からの仲間と出会えて、すごく刺激をもらえたので良かったです。
研究者の方々からは、私達でも分かるように簡単に説明して下さってありがとうございました。実験、実習などを通して新しい知識を得られて、本当に良かったです。
さらに、北海道という自然豊かな場所に行くことで、普段は目にすることができないような風景を見ることなどたくさんのことを体で実感できました。
研究所の方々からは、高校生でするべきことなどの心得を教えてもらえて良かったです。それと、研究者は研究をずっとしているのではないということも言っておられたのに少し驚きました。
自分は、研究職に就きたいというふうに漠然とした将来の希望がありましたが、これからは自分のやりたいと思うことをもっと絞って探すこともとても大切だということが分かりました。でも、色々なことへの知識を持つことは欠かせないことだということも分かりました。
今回のサマー・サイエンスキャンプで、色々なことが学べたのと同時に、心も成長させてもらったと思います。このサマー・サイエンスキャンプで学んだことをこれから生かしていければいいと思っています。
「植物について」(福井県・高校3年生)
未来につなげよう安心な農業と環境~外来植物を探してみよう~
独立行政法人 農業環境技術研究所
農業環境技術研究所のサイエンスキャンプに参加できたことに感謝します。私は当日、不安と期待でいっぱいで会場に入りました。初対面の人達との実習、研究、発表など、うまく交流が出来るか全く自信がなく不安でした。しかし、同じ意思を持った人達との野外実習や、個人の意見をまとめながらのデータ解析や発表は、充実したものになりました。
私が一番印象に残ったことは、野外調査です。どこに外来種が多いかについて仮説検証をして野外に出て調査しました。私は、外来植物はいたるところに生育していて厄介者だと思っていました。しかし、意外と外来植物は少なく、それどころか在来植物であり生育力の強いクズが周りの植物を追い出しているということを知ったことでした。私は外来植物にばかり目がいき過ぎていたことに気づきました。この体験を通して、今後、植物全体の生態系について考えられるように注意していこうと思います。
次に講義していただいた「アレロパシ―」についてです。少々難しかったですが、それらが実在するか否か研究者の方々がさまざまな角度から研究されていることを知り、研究というものは多様な観点から考察することが必要であると私は改めて感じました。また私自身、知識を増やせたことに満足しています。
私は今後、生物や環境に関する大学に進学し、いろんな知識を身に付けたいと思っています。
今回のサマー・サイエンスキャンプは、私の夢の第一歩になったと思っています。このようなすばらしい研修を企画してくださった方々に心から感謝しています。
どうもありがとうございました。
「チームD 2010・富山・我がロボットはこうして産まれた」(神奈川県・高校2年生)
高校生ロボットプログラミング塾「T-1グランプリ2010」
株式会社富山総合情報センター
今回のサイエンスキャンプで自分がやるのは、プログラミングのみだと思っていた。しかし、実際に体験したら、ロボットまで作ることが出来て、大変満足している。自分自身で作ったロボットのプログラミングが出来たことで、今までに体験したことのない達成感が味わえたからである。
自分は、このキャンプの直前まで、東京工業大学の広瀬教授のもとでロボット作りをしていて、この体験を生かせると思っていた。しかし、今回のサイエンスキャンプではロボット作りにとどまらずにプログラムまで作った。自分にとってプログラミングは初めてだったが、大学生などのTAの方々が丁寧に教えてくださったのですぐに理解出来た。
プログラムを作り終え、実際にロボットに情報を送り、走行させてみた。
しかし、ロボットはわがままでコースアウトしてしまった。その時、大学生のTAの方が自分と一緒にプログラムの式の見直しをしてくれた。チームキャプテンを務めた自分は「自分の力でやらせてください。」とTAに言った。するとTAからは「チームでの制作だから、チームの一員である自分たちTAにも考えさせて。」と反応がきた。そのとき、自分は思わず涙が出た。
そして本番。全員の力で作った我らのロボット4台はどのロボットも好調で好成績を残した。その結果、優勝できた。この時チームメンバーの残り5人が自分のことをかこみ「リーダー、おつかれさま。」と言ってくれた。このとき、涙が止まらなかった。この感動・感謝は一生忘れることはないだろう。
このキャンプで施設見学などもでき、充実した3日間を送れた。このサマー・サイエンスキャンプでは、改めてチームワークの大切さを知ることができたので良かった。チームの皆さん、TA、スタッフの方々、本当に感謝しています。
「学んだ事」(広島県・高校2年生)
東自作パソコンを繋げてスーパーコンピュータを作ってみる
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 情報科学研究科
私は以前からパソコンに大変興味を持っている。学校でサイエンスキャンプを知り、そのなかにパソコンに関連する講座があるとわかり、応募してみようと思った。私が選んだのは「自作パソコンを繋げてスーパーコンピュータを作ってみる」というプログラムだ。それまで私はパソコンでインターネットや他のソフトを使うぐらいでパソコンを作るという考えはなかったので、大変興味を持った。
キャンプ初日には色々なパーツを組み合わせてパソコンを組み上げた。
パソコンを作るのは初めてで壊してしまうのではないかと心配だったが、周りが助けてくれて、無事組み上げる事ができた。OSをインストールしていつも見慣れている画面になると安心した。そのときパソコンを自分で組み上げたのだという実感がわいた。
二日目、組み上げたパソコンにプログラムを入力してパソコン同士がつながる環境をつくった。いつもはデスクトップでマウスを動かしてパソコンを操作していたがキーボードからプログラムを入力して操作する方法を学んだ。その方法を知って私は感心した。マウスで操作する方法に慣れていたからこの方法はとても不便に感じたが、慣れるとその方法の方が早いようだ。プログラムのコマンドを学び、実際にパソコンを操作してみたが文字で出てくるだけで本当に内部が操作できているのか心配になった。先生の講義に一生懸命ついていった。
三日目、プログラムも終わって実際にパソコン同士を繋げてみた。パソコンを一台ずつ繋げていくと処理能力が上がっていく実感がわいた。自分でスーパーコンピュータをつくることができたと思うととても感激した。
全国各地から集まったパソコン好きの仲間と先進的な研究機関で勉強できたことは一層パソコンの知識が深まりよい経験になった。このような機会を今後も活かしていきたい。
「自分の考えを説明する力」(神奈川県・高校1年生)
放射光科学の最先端を体験してみよう!
財団法人 高輝度光科学研究センター
僕がこのキャンプに応募した動機は2つある。1つ目は、最先端の施設を見学すること。今回のキャンプでは世界でも1、2を争う精度の放射光が出せる加速器と、現在建設中の次世代加速器、XFELを見せてもらった。実際に見て思った正直な感想は「意外」だった。確かに加速器には精密機械がたくさん並んでいた。しかし、僕は「光速」というものは、とても人間の手には負えないような存在だと思っていたので、目の前にある機械でそれに近いものが人工的に作り出せると思うと、とても意外な気分になり、科学技術の進歩が感じられた。
さて、応募した動機の2つ目は、自分で実験してみること。これは、このキャンプに応募した1番の理由で、普段学校ではほとんど実験をしない分、とても楽しみにしていた。僕が所属した班ではパイナップルに含まれている酵素ブロメラインに関する実験を行った。ブロメラインの抽出から行い、見たこともないような道具の使い方を四苦八苦しながら覚えつつなんとか頭を回転させて、どうしてこの操作をするのかということを考えるということは非常に大変だったが、大変有意義な時間を過ごせたと思っている。
しかし、実験だけでは終わらないのが、このキャンプの醍醐味である。実験で得られた結果をまとめるという作業をしなくてはならない。今回は行った実験のうち、2つの結果が食い違っており、それを説明するのに難儀した。僕は偶然その2つの食い違いを説明できるアイデアを思い付いたが、夜遅くで頭が冴えていなかったこともあり、皆にうまく説明できず、先生に言葉を補っていただき、一応伝わったものの、人に自分の考えを伝える力を普段から鍛えておかなくてはならない、と痛感した。
今回の体験、特に実験や研究者との交流を通して、今まで漠然としか感じていなかった研究者になりたいという気持ちが鮮明になった。今後、機会があればまた参加したい。
「東京湾の魚介類と環境を調べて」(神奈川県・高校1年生)
東京湾の魚介類と環境を調べてみよう~東京湾の本当の姿を実体験!~
独立行政法人 国立環境研究所 環境リスク研究センター
私は、幼い頃からよく祖父と千葉港へ釣りに行っています。しかし、最近は魚があまり釣れなくなってきてしまいました。環境汚濁の問題についてよく耳にしますが、環境はどのように変化し、東京湾に生息する魚介類にどのような影響を及ぼしているのか、自分自身の目で確かめるためにこのキャンプに参加しました。
私は、東京湾にはもう魚介類はあまり生息していないと思っていました。
しかし、実際に海に出て底曳き網をすると、思っていた以上にたくさんの魚介類が採れ、驚きました。東京湾では、横浜の近くであるA地点と、横須賀の近くであるB地点の2カ所で底曳き網をし、採った魚介類をつくばにある国立環境研究所まで持って行きました。種名と個体数重量の調査をすると、A地点とB地点には採った魚介類に違いがあることが分かりました。
採集と同時に測ったそれぞれの地点の酸素濃度、塩分濃度、水温を照らし合わせてみるとA地点の方がB地点よりも酸素濃度が低く、種類が少ないことが分かりました。国立環境研究所の主席研究員でおられる堀口先生は、貧酸素水塊という酸素濃度の非常に低い水が、魚介類の生息に影響を与えていると考え、その原因等を研究していらっしゃるそうです。私たちはグループに分かれ、貧酸素水塊の発生原因等を議論しました。
1つのことについてじっくりと考えることは今まであまり経験が無かったのですが、次から次へと案が浮かび、とても楽しかったです。自分自身で実際に見て、触って、考え、体全体を使って行ったこの研究は、とても素晴らしい経験になりました。研究の楽しさや奥深さを山ほど実感し、とても充実した思い出に残る三日間でした。
「積極性の大切さ」(和歌山県・高校1年生)
先端科学で地球環境を探る─海洋コア
国立大学法人 高知大学海洋コア総合研究センター
初めてサマー・サイエンスキャンプに参加したのですが、とても良い経験になりました。私は、海が好きで海の研究ができるとのことだったので、このコースに申し込みました。まず、実際に研究船で海に出て、普通なら触れることのない器具を使って海底のプランクトンを採取しました。泥を触ってみると、粘土のように感じられました。採集する場所によって土の質が違ったりと、いままで深海の泥を触ったことがなかったので、とても面白かったです。プランクトンの観察でも、学校では使わない顕微鏡を使わせてもらい、プランクトンには色んな種類の生物がいるのだと知りました。また、海底コアのサンプルを、つつの中から採取し、サンプルの中から有孔虫を取り出し探し出すのがすごく楽しかったです。また、有孔虫の中から酸素同位体を取り出し探し出すのがすごく楽しかったです。また、有孔虫の中から酸素同位体を取り出す機械などを見学して、研究することのすごさを改めて感じました。教授の池原先生の講義を聞いていて、すごい研究をしていることが分かり、難しいことでも私たちにわかりやすいよう説明していただき、難しいながらも少しずつ理解することができました。
3日目の報告会のためのプレゼンを作るのに、グループになってパソコンを使いまとめる作業は、私にとってとても新鮮であり勉強になりました。
自分の意見がなかなか言えない場面もありましたが、たくさんの考えや、まとめを見たりすることができてよかったです。また、発表の時、質問にきちんと答えられなかったのが残念でしたが、遺伝子コースの人達の質問の受け答えを聞いていて、もっと積極的に考えを言わなければいけないし、自分の考えに自信を持たなければならないと思いました。
一番良かったのは、他県の人達と出会えたことです。みんなの、将来や今を考えているレベルの高さにおどろいたと共に、刺激を受けました。なので、私にとってこのサマー・サイエンスキャンプは、とても大切な経験となりました。ありがとうございました。
「サイエンスキャンプに参加して」(兵庫県・高校1年生)
光が変われば葉も変わる~樹木の光環境適応戦略~
独立行政法人 森林総合研究所 関西支所
サイエンスキャンプを終えて、振り返ると「楽しんだな」と思います。
1日目、「森林総合研究所とはどういうところなのだろう」と思い興味深く思うと同時に「どんな人が参加しているのだろう」とかなり緊張していました。その後、研究所の方々や引率の先生方、他の参加者の自己紹介や講師の方の講義を聞いたり、実験の下準備をしたりする中で緊張もほどけてきました。
2日目、いよいよ具体的な実験をしました。初めて扱う実験器具ばかりで、発見ばかりでした。特に感動したのは走査型電子顕微鏡です。「これが、葉の断面」と言われた時の感動は忘れられないと思います。1日中、顕微鏡を使ったとしても飽きないだろうと思いました。そして、夜は研究所の方々と一緒に夕食を食べました。流しそうめんを流したり、フランスからの研究者の方と簡単な英語で話をしました。
3日目、実験結果の発表をしました。プレゼンテーションとしては不十分で、悔しかったですが、参考になりました。単位には十分注意します。お土産にもらった「松ぼっくり」は大切に飾ってあります。
ほんとにあっという間の3日間でした。僕はこのキャンプで、技術的なことはもとより多くのものを得ました。つきっきりで指導して下さった研究所の方々、引率の先生、そして3日間を共にした先輩方と出会ったことはかけがえのないものになると思います。またお会いできる日を楽しみにしています。この3日間を端的に表すなら「感動」「感謝」です。僕のつたない文章力では表現できません。サイエンスキャンプと巡り合えて幸せです。
最後に、このような貴重な機会を与えて頂きありがとうございました。次回以降のキャンプにも積極的に応募しようと思います。
「夢への架け橋」(静岡県・高校2年生)
自然の贈り物~野草から薬ができるまで~
国立大学法人 千葉大学 環境健康フィールド科学センター
私は今回、4度目のサイエンスキャンプへの応募で、受かった時は本当に嬉しかったです。その期待通り、とても有意義な体験をすることができました。
まず、全国から集まった同じ志を持つ仲間と学ぶことができたことがとても良かったです。自分と同じくらいの年齢の仲間が、何を考え、感じているのかを知って、とても刺激をうけました。私も、体験したことから多くのことを感じとれるようになりたいと思いました。
フィールド実習や実験の時には、たくさんの野草や生薬の匂いを嗅いだり、試食したりできて、とても貴重な体験でした。私達の身の回りも、薬になる草で溢れているのだと、改めて実感できました。
私の中で一番印象に残っている体験は、煎じ薬と軟膏の作成です。多くの種類の生薬を煎じて作った煎じ薬は、とても苦いものもありましたが、きっとよく効くのだろうなと思いました。黄連解毒湯は、飲めない患者さんのためにカプセルも作っていると知って、本当によく患者さんのことを考えているのだなと思いました。また、私は今まで軟膏はどうやって作るのか全く知らなかったので、実際に作成できてすごく楽しかったです。容器への移し変えも、薬剤師になったようで、早くマスターしたいと頑張りました。
私が参加を希望した動機は薬剤師を目指しているからですが、今まで薬剤師というと、西洋医学を取り扱う病院や薬局で働くというイメージを強く持っていました。しかしこのキャンプで、東洋の漢方学を体感して、漢方にとても興味がわいて、自分で調べたり、大学に入ってからなどに研究をしてみたいと思いました。そして、薬剤師になったら、西洋医学だけにとらわれず、西洋と東洋の橋渡しをすることを目標にしたいと思いました。
三日間、本当に楽しかったです。ありがとうございました。
「サイエンス・キャンプで学んだこと。」(沖縄県・高校2年生)
農楽体験~自然を知る、食を知る、生物を知る~
国立大学法人 高知大学 農学部 及び附属暖地フィールドサイエンス教育研究センター
私は今回参加した「農楽体験~自然を知る、食を知る、生物を知る~」で、普段の日常生活や学校では学べない農業のことをいろいろ学び、そして貴重な体験をすることができました。
まず、初日の最初の講義である曵地先生のお話で、私を含めメンバー全員、度肝を抜かれました。単なる農業だけの話でなく、これからの世界の食糧危機の深刻さや、日本の先進国の割に低すぎる自給率など、私としてはとても心配になる話がたくさんありました。これからの日本とそれを取り巻く環境と、そして世界について深刻に考えるべきだと感じました。
そして私がこの授業で、完璧に考えが180度変わり、驚いたことがあります。それは、「遺伝子組換え作物」についてのことです。それまで私は、遺伝子組換え作物は、聞いた感じ何となく、危険で悪いものだという意識がありました。けれども今そう思っているのは日本だけで、世界ではどんどん遺伝子組換えが広がっています。それともう1つ、私は自然が地球から生まれもった遺伝子を、人間の手で変えるのはどうなのだろう、という倫理的な立場からみた抵抗もありました。だけどレタスは菊の突然生まれた変種であり、そしてそれを人間が食べているという話を聞いて「ああ、こんなこともあるのだ。人間が変えることがなくても、自然界で突然変異が起こることがあるのだ。」と新たな発見に驚き、ほっとしたのを覚えています。
曵地先生の話だけでなく、高知県の和牛に実際に触れて生命の鼓動を感じたり、沖縄に住んでいる私には貴重な体験である稲刈りをしたりコンバインに乗ったり、充実した三日間を過ごすことができました。夜のミーティングでいろんなことを話し合って、同じ志を持った仲間たちと語り夢の話が聞けて良かったです。私はこの三日間で様々な視点から見る事の大切さに気付けました。このキャンプに参加することができて良かったです。
「出会いと感謝」(兵庫県・高校3年生)
アサリ研究のフィールド体験
独立行政法人 水産総合研究センター 中央水産研究所
私がサイエンスキャンプに参加するのは二回目なのですが、やはりあっという間に過ぎるように感じる3日間でした。しかし、とても密度の濃い3日間で思い返すともっと長い日にちがたったようにさえ感じられます。
1日目には、アサリやマイワシに関する講義や、調査船蒼鷹丸や施設の見学をさせていただきました。講義では知識だけではなく、自分で見て、考えることや出会いを大切にすることなども教わりました。2日目には、実際にフィールドへ出て、調査や試料採集を行いました。調査したフィールドには、本当にたくさんのアサリがいて、手堀りした時に指先に当たるアサリの感触に驚き、またすごく興奮しました。フィールドワークの後は、研究所へ戻りグループに分かれて実験を行いました。私のグループでは、カオリンや分光光度計を用いたアサリのろ水速度の計測だったので、アサリのろ水活動中は他のグループを見学したり、少し参加したりしていましたが、午前に行ったフィールドワークの疲れのせいか待ち時間がとても長く感じられました。しかし、水中で活発に動くアサリを見たり、徐々に綺麗になっていく様子を観察しているととても興味深く感じました。3日目には、その結果をグラフにしたのですが、思ったより難しく、時間がかかってしまい、作成してみたいグラフや出してみたい数値を全て出せずに終わってしまいました。なので、時間がある時に電話やメールで聞いてみようと思っています。しかし、それでも分かったことは多くあり、特に小さなアサリのろ水能力にはとても驚きました。
同世代の仲間達と出会い、いろんな話をできたこともとても良い出来事でした。最後に、大学やその先に活かせる経験をさせていただいてありがとうございました。
「サイエンスキャンプに参加して」(岡山県・高校2年生)
希少糖をとおしてみるバイオの世界
合同会社希少糖生産技術研究所
私がこの希少糖についてのキャンプに行きたいと思った理由は、もともとバイオに興味があり、希少糖について何も知らなかったので、勉強したいと思ったからです。希少糖生産技術研究所でのサイエンスキャンプは初めてということで、慣れていなくて説明などが分かりにくいのではないか、という不安もあったのですが、分かりやすいテキストを使い、とても分かりやすく面白い講義をして下さって、ちゃんと理解することができたと思っています。このキャンプでは、希少糖研究の第一人者である何森先生の講義を受けることができたのが、すごく良い経験になりました。IzumoringPadというものを作って、HとOHの場所が少し違うだけで全然別の糖になることにすごく驚きました。希少糖生産技術研究所では、酵素を用いた希少糖の生産技術を研究していたのですが、中庭に「ズイナ」という植物があって、この葉100gから3gの希少糖が取れるそうです。そういう不思議な木があることにも驚きました。
今回のサイエンスキャンプで得たものは、知識や経験だけではありません。同じキャンプに参加した人とは初めて会ったけど、すぐに仲良くなって、たくさんの思い出ができました。講師の先生やアドバイザーの先生など、お世話になった方々も本当に面白くて優しくて、本当に行って良かったと思いました。夜に行ったミーティングでは、皆がちゃんと理解して帰れるように、アドバイザーの先生が皆に質問をしたりという時間もあって、すごく充実した時間が送れたと思います。
私は今回のキャンプで、自分にしかできない考えを探そうと思いました。
何森先生がおっしゃっていた「世界的研究とは、自分しかやっていない研究のことだ。」という言葉が強く印象に残っています。これから私は、研究者を目指して、日々「自分にしかできないこと」を探し続けようと思います。
「キャンプに参加して」(沖縄県・高校3年生)
地球温暖化シュミレーション~NASAの気候モデルにチャレンジ~
桜美林大学 リベラルアーツ学群
私が今回、参加した理由は、内容に興味があったのと、大学で学ぶための足がかりとして、でした。私は将来、自然環境の分野に進みたいと考えていたため、このキャンプの内容はとても興味深いものでした。 参加した初日は、緊張しており、ちゃんと授業が理解できるのか、他の生徒と打ち解けられるか不安でした。しかし、授業はとても分かりやすく、他の人たちもとても親しく接してくれました。特に坪田先生の説明はとても分かりやすく、楽しかったです。内容は主に地球の大気系から地球温暖化へのアプローチでしたが、水蒸気も温暖化の原因の一つ、熱の放射の仕組みなど、とても驚かされるような内容が沢山でした。 二日目には、タイトルにものっていたEdGCMを本格的に使って実習を行いました。システムを使っていくうちに、今の技術の高さに感動しました。 また、シミュレートをした内容の中で特に興味深かったのは、CO2濃と気温の変化、氷の変化でした。CO2が増えていくほど気温が上がっていくのは予想通りでしたが、氷の厚さがあまり変化していない、というものでした。その他にも色々なデータが出て、今まで考えていた結果はもっと調べてみたいと興味がわきました。その後も、先生の説明、グループでの実験と、二日目は一番楽しく、学べた一日でした。 三日目の発表は、うまくまとめられず、グループの皆には迷惑をかけてしまいましたが、協力して作ることができ、また知識の整理としてもためになりました。他のグループからも気づかされることも多く、聞いていて参考になりました。 私は、このキャンプで、益々地球温暖化への意識が高まりました。また、他人と接したり、新しい知識を得ることで、知識や視野も広げることができました。今回お世話になった先生方や大学生の方々には感謝の気持ちでいっぱいです。