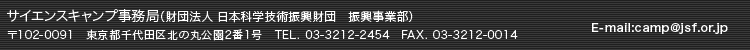「今回の有機EL研修が導く将来」(山形県・高校1年生)
有機の光で照らしてみよう~有機ELを作る~
国立大学法人 山形大学大学院 理工学研究科 有機デバイス工学専攻
今回この行事に参加してみて「我が地元にはこんな科学の最先端研究があったのかっ!!」と驚いてしまった。元々有機ELについてはそれがどういったものか、どこでやっているのか、それを応用するとどのような事が出来るのか等は知っていた。しかし…、私はそれに対して実のところ「製品化?そんなの無理だろ」と懐疑的であった。しかし、その認識が変わったのは米沢駅で見た有機ELの展示物を見てからである。それはとても薄いのにとても明るかった。それを見てから私は有機ELに興味を持ち、今回参加した。
2日間の実験はとても楽しく興味深いものであり、また内容の濃いものだった。私は正直、有機ELのAlq3の分析や蛍光スペクトルについて等、分からない事が多々あった。しかし、そういった疑問を院生の方はとても分かりやすく教えてくれて良かった。有機ELの製造で自分たちの班の有機ELが黄緑、青どちらもとても鮮やかに光った時の感動は忘れられない。自分の班が1位になれずに残念だったが、それもいい思い出だ。
実験の合間の休憩中に私は初めて見たものがあった。一つは有機ELテレビ、もう一つは避難灯だ。テレビについては新聞、ニュースなどで見たことはあった。しかし生で見たのは初めてで、その映像はこれまで見たことが無いほど美しく、そして薄かった。避難灯は光ることはもちろんのこと、避難を促す音を有機ELで流すという事に驚いた。それらの価格は未だ高いが、しかし実験や講義を聴いた後に見ると安いぐらいだと思った。
3日目に行ったクリーンルームについては、私が昔から入ってみたかった場所に入れたという感動があった。中にある有機ELを製造するための機器の価格にも驚かされた。
私は今回の経験を通して、より一層科学に対する知的好奇心が湧いてくるのを感じた。将来どのような研究をするかは分からないが、決して無駄にすることは無いと思う。
「サイエンスキャンプで得たもの」(神奈川県・高校2年生)
マイコン制御ロボットをつくろう
神奈川工科大学 創造工学部
私は、このサイエンスキャンプで自分の視野が広がり、将来の為になればと思い参加しました。ロボットの「ロ」の字も知らずに行くことを決めたので、入門書を読んで勉強しようとしましたが、何が何だか分からず、初日は私のような奴が行って場違いではないだろうかと不安でいっぱいでした。
しかし、その不安も大学へと向かうバスの中でふっ切れてしまいました。優しく、理解できるまで教えて下さる教授と大学生が居たからです。それに初日に学んだ「マスタースレーブロボット」はとても勉強になるもので、講義は難しかったですが作製に入ると細かい作業がとても面白く、夢中になってやっている自分がいました。夜には大学の方々との交流会があり、ビンゴで盛り上げて下さいました。そこで大学生の方に学生生活のお話や入試のことも詳しく聞くことができて、有意義な時間を過ごすことができました。
サイエンスキャンプの中で、最も頭を使ったのは2、3日目に行った「マイコン制御ロボット」の製作です。どのように工夫をして設計をすれば課題をクリアできるのかとても悩みました。2人1組での活動だったので、ペアの子の足を引っ張らないように、しかし自分の意見も上手く伝えければいけないので、今思えば2泊3日ではとても時間が足りませんでした。2人で試行錯誤して、やっと完成したロボットは残念ながら、納得のいく結果を残すことが出来ませんでした。しかし私は、この製作を通してロボットは1人の知識と体力では作れず、他人との協力が必要だということが分かりました。そして、決して成功する訳ではないということを知りました。ペアの子が「悔しいなぁ」と口を噛み締めているのを見て、ロボット製作は奥が深いと感じました。この2泊3日という短い期間で私は、多くのことを学び、自らの視野も広がりました。サイエンスキャンプのお陰で私は、将来がとても広がった気がします。
「次につながる驚き」(東京都・高校1年生)
体験しよう!風力発電の技術
国立大学法人 鳥取大学 産学・地域連携推進機構
風力発電、それはプログラム参加前の私にとって、壮大でどこか遠くにある技術に感じられました。地球に負担をかけずに開発するための技術を学びたいと思い、私は今回のプログラムに参加しました。
参加前、私は風車を早く回すほど大きな発電量が得られると思っていました。しかし効率良く発電するための鍵は速度だけではないと知り、ゆっくりと回る風車をもどかしく感じていた私には新鮮な驚きでした。初日の見学では初めての大型風車を目の当たりにしました。風車の真下に立ち、百メートルを超えるその大きさに圧倒されました。そして同時に軽い頭痛を感じました。風切り音と低周波音の問題はプログラム前から知っていましたが、体感できるとは思っていませんでした。クリーンな反面、まだよくわかっていない課題があるということがわかりました。風車がより普及するためにはこのような問題を解決する必要があり、それは私達の仕事なのだなと思いました。
3日間の中で私にとって一番大変だったのは、実験結果から考察をする、という作業でした。私たちに与えられたのは結果として表れた数値のみ、そこから自分なりに考えを導き出すというのはおそらく初めての体験でした。これまで考察だと思っていたものは行き先が示された道の上を走るようなもので、ゼロから考えていく今回の考察が本当の考察であり、研究をしていく上では当たり前のようについて回るということを知りました。悩みに悩み「わからない」を連呼しながら考えをまとめた数時間は価値あるものだと思います。
本物の研究の現場を少しだけ覗くことができ、学校での勉強だけが全てではないのだと実感しました。今回このプログラムに参加して得た数々の「驚き」を私の大切な財産にしていきたいと思います。
「いくつもの発見が生まれた体験」(大阪府・高校1年生)
加速器による、素粒子から身近な物質までを探る研究を体験
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構
「広い!」高エネ研に着いてまず思ったことです。このような公的機関に泊まりがけで学びに行くということは初めての体験だったため、いざ、足を踏み入れると最先端の研究施設に来たのだと急に実感がわいてきました。
施設見学でもそれぞれの施設において、担当の教授の方が熱心に解説してくださり、2時間という時間ではとても足りないほど、とても密度の濃い時間でした。
2日目の実習では「低温」コースに参加し、物質の性質が温度によって大きく変化する例を、実験を通して体験しました。高温超電導物質を液体窒素で冷却すると、磁力に反発し、磁石の上で浮く現象などを分かりやすく解説していただき、凄く興味を持ちました。そのあとの液体ヘリウムを用いて、3種類の金属の電気抵抗を測定する実験では、温度が安定するまで2、30分待ち、表示される電流と電圧を記録し、抵抗値を出すという一連の作業の繰り返しで、すごく忍耐力のいる作業でしたが、結果、超伝導物質の抵抗が、ある一定の温度まで下がると、いきなり0となり、超伝導状態となる様子を観察することができ、すごく興味深かったです。驚きと感想の連続で、これこそが研究なんだと肌で感じました。
普段は絶対みることができない最先端の技術に触れることができ、すごく貴重な体験ができました。このキャンプを通して学んだことは「なぜ?」をそのままにしないということです。分からない所は、どんどん先生に質問して、吸収することができるのがこのキャンプの醍醐味だと思います。さらに実験を通すことにより、より確かに理解を深められ、最終日の発表では、キャンプで得た知識を自信を持って全体に発信することができました。
他県の学校の人とも交流でき、楽しく有意義な、あっという間に過ぎた3日間でした。
将来の可能性が見出せる出来事に参加できたことに深く感謝します。この体験で生まれた発見をこれからも生かしていきたいです。
「本物に触れて初めて分かったこと」(岩手県・高校2年生)
生きていることと生きること~遺伝子の世界と脳の世界~
独立行政法人 産業技術総合研究所 脳神経情報研究部門
今回のサイエンスキャンプは、今まで教科書や言葉でしか知らなかった世界を実際に体験し、具体的なイメージを掴み、新たな発見が出来た貴重な体験でした。
まず、遺伝子の一部を変えれば仕組みも変わるということは当たり前の事ですが、遺伝子の一部を変えた線虫が他の線虫に絡みながら行動したり、普通の線虫に比べて細くなったりと行動や形態上に変化が見られました。遺伝子のたった一部を変えるだけで、どれほど大きく影響するのかが分かり驚きでした。もし人間で行ったらどうなるのだろうと考えさせられる観察でした。線虫の観察もニワトリ胚の観察も命をいただくことですることができる実験です。必要な知識を得るために、必要最低限の命をいただいて、必ず自分のためにしなければならないと思いました。
また、講義では「細胞は孤独」だと教えていただきました。私が今まで細胞に持っていたイメージは細胞分裂でどんどん増えてゆく群のようなものでしたが、細胞は細胞膜でそれぞれ囲まれ、孤独な状態にあるので外界とのやりとりが不可欠という事が分かりました。このやりとりのひとつの例がNa-Kポンプです。ポンプが能動輸送をすることは知っていましたが、それが細胞内外の電位差のために起こっている事は初めて知りました。他にも神経細胞では電気により情報のやりとりがされていました。人間は1人では生きてゆけないとよく言いますが、細胞レベルからのことなのだと思いました。
講義と実験を通し、今まで言葉上では知っていた事でも、実際の体験でしか学べない事がたくさんあり、体験することで出てくる疑問もありました。まだまだ生物は不思議な事を秘めていると思い、同時にもっと生物の事を知りたいという気持ちも強まりました。サイエンスキャンプに参加できてよかったです。本当にありがとうございました。
「新たな発見と知識~私の中でタンパク質と同じように光った探求心~」(香川県・高校1年生)
試験管の中で生命をつくる~遺伝情報とタンパク質~
国立大学法人 愛媛大学 無細胞生命科学工学研究センター
私は今回がサイエンスキャンプの初めての参加でした。学校の生物の授業の応用も自分で勉強していたのですが、いざ実験が始まってみると、初めて聞く用語や薬品の名前ばかりでとまどいました。でも、TAの方が優しくていねいに教えてくださったので実に実験を進めていくことができました。実際に自分で作った発光タンパク質を見たときの嬉しさはずっと忘れません。大腸菌への遺伝子導入で大腸菌が発光タンパク質を作ることのプラスミドDNAの分析が最初は理解できなかったのですが、大学生の説明をきいて、なぜ途中から一定の長さにしか伸びなくなるのかという理由など「PCRによるDNA増幅の原理」は他の人に説明できるくらい理解できました。また、私の班が担当していたタンパク質の分析については班の人たちとTAの方と話を深めていくことで電気泳動の実験の結果もよく読み取れました。MALDI-TOFMSのデータとも対応させて、より確かな結果を見ることができました。実験をすることによって自分で一連の流れを体験し、結果を分析することによって自分で一連の流れを体験し、結果を分析することによって自分の中での理解が深まり確かなものになることがよく分かりました。実験の前後の先生方のお話も、私たち人間にとても深く関連している内容で、興味をもちました。なにより先生方の人柄や研究に対する熱意にひかれました。私も将来、何かに大変な興味を持ちそれを探求していくことができるような人になりたいと思いました。この3日間で、大学の先生方、大学生、全国から集まった高校生と交流をして、さまざまな実験をして、と、とても充実した時間を送ることができました。今回のサイエンスキャンプは、私にたくさんのことを学ばせてくれました。参加して本当によかったと思います。タンパク質の実験、小麦胚芽の無細胞の最先端の実験とてもよかったです!!これから私も、もっと詳しく勉強します!!3日間、先生、TAの方、その他大勢の方、ありがとうございました。
「関係する科学」(埼玉県・高校2年生)
先端機器で拓く身の回りの科学
国立大学法人 福岡教育大学 理科教育講座
なぜ3日間で地学、化学、生物と3つの分野を行うのだろう、と少々の疑問を参加当初はもっていました。それは3つの分野は全く異なったもので、関係をもつことがないと考えていたからだと、キャンプ終了後に思いました。実際は地学でのスペクトルは、化学の白熱灯、蛍光灯、LED灯とでスペクトルの見え方が異なるといったことに関係し、DNAの析出では、DNAの化学的性質からエタノールを使用するなど、3日間学ぶ分野が目まぐるしく変わったことにより、すべてが関係しているということが身をもって分かりました。そして地学、化学、生物といった専門分野に進んだとしても、基礎となる他分野の知識も必要となってくるのだなと、普段の勉強の大切さを強く感じさせられました。
福岡教育大学でのサイエンスキャンプでは、高校では見られないような多くの研究施設、研究装置の性能などに先端技術の凄さを感じ、驚かされました。また研究者の方々のお話も多く聞くことができました。研究者として必要となる考え方、視点などといったお話から、どのような過程を経て教授になるのか、また研究者には英語、文章能力も必要だということなど、研究者には1つのことだけでなく、様々な能力が必要であると聞き、研究者になりたいと思っていた私は今の自分に必要なこと、やるべきことなどが具体的に分かりました。また教授先生、TAの方々の生き生きとした姿は私に研究者を目指すことの後押しをしてくれたと思います。
今回のサイエンスキャンプに参加し、研究者になりたいという気持ちがとても強まりました。先端技術の詰まった研究装置を使用し、自身の好奇心に突き進み、未だ解明されていない事象を追う姿にとても刺激を受けました。私もまた自身の興味のあるものに対して、考え、考え、考え抜いて多くのものを得られる研究者になれるよう、今自分がすべきことを精一杯に頑張りたいです。
「内容の濃い3日間」(埼玉県・高校2年生)
超伝導を作ろう~高温で見い出された超伝導の謎~
国立大学法人 北海道大学 大学院理学研究院
僕がこのウインターサイエンスキャンプについて知ったのは、学校の掲示板に貼られていたビラを見た時でした。ビラには様々な講座がありましたが、僕は超伝導に惹かれました。小さな頃に山梨リニア実験線の試乗会に応募したことや、その時に知った超伝導のことを思い出し、再び関心を抱いたからです。
応募が通り、行くことになった当日、僕は他の参加者のことを考え、とても緊張していました。しかし夕食時の顔合わせですぐに仲良くなることができ、ほっとしたものです。大学では、教授の方々による講義や実際に超電導体を作る時があり、講義においてはお話しされる内容はとても難しかったのですが、質問に親切に答えていただき、これまで超伝導について所々しか知らなかった細かい原理が理解できました。この時聞いた超伝導が今ではMRIに用いられているということにはとても驚いたものでした。また、超伝導を作る時には、あらかじめTAの方々が初期段階を済ましていたということもあり、特に難しいこともなく、そして長時間ずっとこすり続けるという作業であったため、そのしばらくの時間、TAの方々と大学での生活についてお話しすることができ、とても楽しい時間になりました。作成中には、自分の作品がきちんと超伝導体になるのか不安でしたが、1日後に取り出し、冷やしてから恐る恐る磁石に乗せると浮かんだ時には少し感動もしたものでした。そうしているうちにすぐに閉講式の時間になってしまいました。僕は今回とても早く時間が過ぎていったように感じます。閉講式の後、僕は一緒に過ごした仲間たちとメールアドレスの交換をしてから別れました。
このような短期間に別の学校の人たちと仲良くなれたり、実際に大学の方々と身近に交流できる機会は滅多に無いことです。僕はこのウインターサイエンスキャンプを有意義に過ごせました。
「初参加を通して…」(千葉県・高校2年生)
雪と氷の世界を体験しよう~雪結晶から地球環境まで~
国立大学法人 北見工業大学 工学部
参加しようと決意してからこの感想を書くまでの道程は、思い返せばとても短いものでした。僕が最も興味を抱いていた地学が勉強でき、しかもフィールドワークができるという2つの点が、僕の目にとまり、離れませんでした。そのため選考通知が届いたときは、この上無い程の喜びを見い出していました。
参加するにあたって、まず出会った壁が「不安」というものでした。飛行機にはちゃんと乗れるのか、参加者や講師の方々とはうまくやっていけるのか、といったような不安が僕自身を取り巻いて、出発前日は睡眠が十分にとれないほどでしたが、無事に会場に着くこともでき、最も心配だった参加者とのやりとりも、皆いい人ばかりですぐに打ち解けることができました。
1日目は大学の研究施設に併せて、メタンハイドレードと呼ばれる、燃える氷についての説明を受けたり、路面の凹凸を評価したドライビングシュミレータに乗車したりしました。夜の講義では、雪一粒の物質的な事柄や、翌日の山歩きの事前学習をしました。
2日目は、僕が1番待ち望んでいたポンポン山の探索や地熱・硫黄噴出口の温度測定を行いました。硫黄山では、湧き出た源泉に手を浸して皆で温まったのを覚えています。ポンポン山で地熱の測定を終えたあとに聴くことができた、雪解け水のせせらぎに重なったマダラスズの鳴声は、とても神秘的でした。
ついに3日目、グループ発表を行いました。さまざまな方言が飛び交う中での前夜からの話し合いによって、完璧とは言えぬも完成度の高い発表をつくり上げることができました。
3日間を通して、いろいろな知識を得ることができ、更に地学に興味を持ちました。また、それだけでなく、他人との関わりや協力の重要性を学ぶこともできました。今回の参加を機に、身近な事柄を深く考え、更に理科に興味をもち、自分自身に磨きをかけていこうと思いました。
「守るための科学技術」(奈良県・高校1年生)
携帯電話から金をとりだしてみよう
国立大学法人東北大学 大学院工学研究科 創造工学センター
中学2年生の時、学校の自由研究で調べた子供兵のこと。多くの人が知らないと思われるこの事実こそ、私がこのサイエンスキャンプに参加するきっかけになりました。子供兵とは、レアメタルなどの鉱物資源をめぐる紛争で無理やり戦わされている子供たちのこと。「貴金属のリサイクル」と聞いて真っ先に思い浮かべたのは、この子供兵のことでした。
レアメタルのリサイクルは最近とくメディアなどで取り上げられ、いわゆる「都市鉱山」と呼ばれるものに私はとても興味を持っていました。そこでこのキャンプを知り、私は飛びつくように応募しました。
はっきり言って体験した実験は、予想を大幅に上回る楽しさで、私は始終興奮しっ放しだったように思います。学校では発揮したことのない、ものすごい集中力で講義を聞いていた自分に我ながらびっくりしました。
金をとり出せた時の感動は、今まで感じたことのないものでした。金の粒だけを見ればとても小さいけれど、たった3gの携帯スクラップからこれがとれると思うと、このリサイクル法のすごさを実感しました。
私はこのサイエンスキャンプで資源リサイクルの可能性と重要性についてとても考えさせられました。私たちが普段当たり前のように使っている携帯電話。それが作られる背景には、環境、文化、伝統、命など多くの犠牲があり、そしてそれらを踏み台にして私達の豊かさが成り立っていることに気づきました。
このリサイクルを普及させることによって経済的な面だけでなく世界で起こる様々な紛争を減らすことにもつながるのではないでしょうか。そのためにはやはり科学技術の発達というのはとても重要なことなのです。
環境、文化、伝統、命。これを壊してしまうのも科学技術ですが、これらを守ることができるのも科学技術なのです。壊すことよりも、守ることを見据えた科学技術こそ、今後世界が求めるものなんじゃないかと思います。