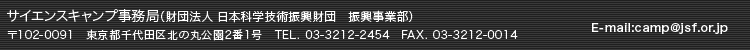「最先端の研究をめざして」(神奈川県・高校2年生)
超伝導を作ろう~高温で見い出された超伝導の謎~
国立大学法人 北海道大学大学院 理学研究院
実験では、磁力線を通さない目に見えない力を見て、感動しました。しかし、よく考えてみると重力も目に見えない力の1つですので、『力』というものの不思議さを改めて感じました。
講義はとても判りやすく良かったです。でも、自分が聞いても判らない様な難しいお話を想像していたので、少し残念でした。実際に研究している先生方から最先端のわからないような話もお聞きしたかったです。
けれど、2日目の懇親会で、先生が「登山家がそこに山があるから登るのと同じように、物理があるから学ぶんだ。そしてその山の頂上に到った時、初めて美しい景色が見える様に、物理も最先端の研究をする時に初めてその楽しさが判るんだ」と仰ったことを覚えています。私はまだまだふもとにも及びませんが、いつか先生の言った事が「あぁ、この事だったんだ」と気付く日を迎えるために頑張っていきたいと思いました。
今難解な講義を聞くことが必要なのではなく、こういう思いを持ち帰ることこそが必要だったのかもしれないとも思います。自分と同じく参加した人たちは、超伝導に関しての知識だけでなく、様々な事を知っていて、自分の無知を知り、恥ずかしくなったと同時に、もっと勉強したいと思いました。
「自分で考え行動すること」(大阪府・高校2年生)
雪と氷の世界を体験しよう~雪結晶から地球環境まで~
国立大学法人 北見工業大学 工学部
「私の中で様々なことが大きく変化した」キャンプに参加して私が一番思ったことです。
最先端の技術を知る先生方に多くのことを教えていただきました。特に、天然の冷蔵庫のような北海道の大自然の中でのシャボン玉を凍らせる実験。あの時見た美しく凍ったシャボン玉は、一生私の心の中で輝き続けると思います。
そして、静電気を発生する機械に雪を振り掛ける実験。機械に当たるやいなや反発し、跳ね飛ぶ雪は、とても不思議でした。どうしてそうなるのかと私が質問したところ、先生の「どうしてそうなるんだと思う」という言葉。新しいことを知るために、物事に対して疑問を持つだけでなく、自分で考え行動することが大切だということがわかりました。そうすることによって知識を得、深めることこそが本当の意味での勉強であると知りました。
さらに、良き仲間達との出会い。他県の人と話をするだけでこんなにも刺激を受けるとは思ってもみませんでした。高校生時代にこんな経験ができることを幸せに思いました。
また全員で登ったポンポン山。雪の重みで下へと枝を伸ばす樹々が沢山生えていました。本で読んだ、雪が自然物に与える作用を実際見ることが出来ました。
サイエンスキャンプに参加して、本当に自分が成長したと思います。そう考えると心の底から感謝の気持ちでいっぱいです。
「ひと冬の科学」(神奈川県・高校2年生)
種々の気体の粘度を測ってみよう
国立大学法人 東北大学大学院 工学研究科 創造工学センター
実は、今回のサイエンスキャンプ参加に関して、親から勧められて応募しただけで、「3日間も自分の自由な時間を割くなんて…」などと考えたりもしました。しかし、プログラム前の研究室訪問で最初の研究室に入った瞬間「これは来てよかった!」と思いました。
プログラムのメイン実験では、装置自体はそんなに難しいものではなく、実験の操作も簡単でしたが、実験の計画、方法がさすがに高校とはレベルが違うと感じました。正確に計測し、その値を公式に代入して求めたい値を出す。文章にするとたったこれだけですが、正確に計測するための工夫、公式の成り立ち、エクセルによる計算など様々なことを学ぶことができました。実際に実験によって何種類かの気体の粘度を測りましたが、仮説や文献のデータと大きな違いが出てしまったものがあり、なぜそうなったのか、どこをどう改善すればより正確な値が出るのかということを本気でじっくりと考えることができました。
また大学生、大学院生の方や先生方との話では、将来の進路について参考になることがたくさんありました。自分は理学の気象の方面に進みたいと考えていましたが、工学への興味がすごく高まりました。
そしてこのサイエンスキャンプで全国各地の人と知り合えたことがよかったです。志の高い人、積極的な人など、自分と違うところを持つ人に会えたことは、これからの自分のためになると思います。
「Precious time in 山形 !」(東京都・高校2年生)
有機の光で照らしてみよう~有機ELを作る~
国立大学法人 山形大学 工学部 機能高分子工学科
私はふとしたことから有機ELに興味を持ち、今回のサイエンスキャンプに応募しました。城戸先生は有機ELの世界的権威であることを知り、その研究室のスケールの大きさに驚きました。実習はというと、感動と驚きの連続でした。はじめて見る蛍光物質を合成し、紫外線をあてるとその物質が黄緑色に光るのです。その光は鮮やかで本当に神秘的でした。有機ELを1つ作成するのも、たくさんの時間と労力が必要でした。しかし、最後に自分達の有機ELが光ったときはみんなで歓声をあげました。
有機ELは、今、研究真っ只中です。有機ELを使った商品も次々に出回っています。しかし、それに至るまでにはたくさんの壁があり、それを乗り越えて今の有機ELがあるのだそうです。そして、まだまだ超えなければならない壁もあり、それに城戸先生は苦労していました。私がこの3日間で学んだことは、どんな壁にぶち当たっても乗り越えていく努力です。これ以上無理だと思っても、自分の知識をフル回転させ成功に持っていく、これは研究だけでなく様々なことにおいて大切なことです。サイエンスキャンプで学んだことは絶対に忘れず、自分の将来につなげていきたいです。
「“夢”を組み立てる」(岡山県・高等専門学校1年生)
自立型ロボットをつくろう
神奈川工科大学 工学部
このサイエンスキャンプで特に私が深く学ぶことができたと思うことは、自分の手で一からモノを作り上げることの素晴らしさです。
3日目の午後に行われるロボットコンテストに向けて、参加者それぞれが自立走行ロボットを作るのですが、課題をクリアできるようなアイデアを練り、車体やプログラムを作るという工程をすべて自分ひとりだけでやらなくてはならず、とても苦労しました。
しかし、大学生の方や先生に助けられ、参加者の仲間と励ましあいながら夜遅くまでロボットを作ることはとても有意義で、勉強になり、言葉にすることができないほど、楽しかったです。そして、例え散々な結果だったとしても、そうして作ったロボットはとても愛しくて、それを共に作った仲間は、本当にかけがえのないものです。
自分のアイデアを、誰にも邪魔をされずにカタチにできる機会というのは、こういう場を除いてはあまりありません。社会へ出れば、必ずしも自分の意見が採用されるわけではないでしょう。でも、今回のサイエンスキャンプで学んだ、問題を解決するためにアイデアを練り、試行錯誤し、仲間と協力し、ひとつのモノを完成させるということは、これからの学生生活でも、社会に出た後にも、必ず役に立ってくれると思います。
このキャンプを通して、私はとても成長できたと感じました。こんな素敵な体験を、もっともっとたくさんの人にしてもらえることを願っています。
「「就職」派から「進学」派へ」(滋賀県・高校2年生)
体験しよう!風力発電の技術
国立大学法人 鳥取大学 地域共同研究センター
今回、最も良かったことは、大学の設備を生で見られたことです。他校の生徒との交流や風洞実験・実習内容のプレゼンテーションもすごく魅力的な内容で濃い3日間のプログラムでした。私は就職にしようか進学にしようかと悩んでいて、最近になって、就職にしようと思っていました。大学というものを良く知らないし、就職なら、わざわざ大学を卒業しなくてもいいだろうと思ったからです。しかし、サイエンスキャンプに参加して、その考え方が大きく変わりました。大学で見て、聞いて、学んでいる間に、大学はおもしろいんだな、高校では、こんなことはできないだろうなと思えてきました。
そして、2日目の小型風力発電機を用いた風洞実験でさらにその思いが高まりました。風洞という風力を調節して風を送り出す機械の前に、自らが作った小型発電機を取り付け、決められた風力で回転数と発電量を計測する作業でしたが、思ったようにはいかなくて、少し残念でした。しかし、大学に入ればまたこの研究ができますし、もっとより深い知識を手に入れることができるとわかり、自分の中では良かったと思っています。
3日目のプレゼンテーションで3日間一緒に学んできた他校の友人の発表を見て、いろいろなことを学びました。発表をする姿勢、仕方、惹きつけるコツや話術、わかりやすくするための工夫などを学びました。このメンバー全員と同じ大学で勉強がしたくなりました。
「自然を科学する」(福岡県・高校1年生)
生命の海を科学する~海洋のミクロ生態系~
国立大学法人 愛媛大学 沿岸環境科学研究センター
「サマー・サイエンスキャンプに参加したんだけど、東京へ行けたし他の地方の子とも友達になれたし、すっごく楽しかったよ!」
ウインター・サイエンスキャンプに参加したのは、友人のこの言葉がきっかけでした。
私達は日ごろどうしても授業を受ける際「聞く」ことに徹しがちです。実験でも「これは何を調べようとしているのか」「この結果から何が分かるのか」と尋ねられると答えに詰まることもあります。それは物事を「受け身」の体勢で聞いているからだと思います。
「どうして海では川より植物プランクトンが多いのですか?」と聞いた私に対し、先生は「どうしてだと思う?」と逆にお尋ねになりました。当初は早く教えてくれればいいのにとも思いましたが、あれでもないこれでもないと数時間考えたあげくに答えに辿り着いた時の喜びは今でも忘れられません。1つのことを知ってこれほど嬉しかったのは最近では久しぶりでした。
小学校から中高と進むにつれ理科は暗記科目としての側面が強くなり、昔科学図鑑を広げ水の波紋やボイジャーの木星写真を見た時の「世界にはこんなにも不思議なことが沢山あるんだ!」という胸の高揚を忘れかけていました。今回の体験をきっかけに、いつまでも「自然を科学する目」を持ちたいと思います。
「様々な角度から見て考える」(岩手県・高校1年生)
宇宙の謎に迫り、物質の構造を探る加速器の世界に触れてみよう!
大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構
サイエンスキャンプの体験を今後の学習に活かしたい、それは、班別実習をしている時に感じました。私たちのグループの実験内容は光の回折現象を使って、目に見えないものを見ることでした。実際に実験してみて、実験自体は簡単なのに、その結果や実験過程などを様々な角度から考察することができることを知ってとても驚きました。そのように角度を少しずらして見るだけで、回折格子の間隔や格子の種類など、いろいろな分野の研究につなぐことができることが分かり、これからの研究や学習をするときも、このように様々な角度から見て考えれば、新しい発見があるかもしれないので、応用していきたいと思いました。そして、この研究をいろいろな場面で活かしたいと思いました。
私は高エネルギー加速器というものを少ししか知りませんでしたが、講師の研究者の方々などに丁寧に教えていただいて、高エネルギー加速器のことや、高エネルギー加速器研究機構で何を研究しているのかを知ることができました。
また、初対面の人たちと一緒に活動することができるか不安でしたが、話をしているうちに、少しずつ仲良くしていくことができました。とても楽しかったです。このような経験があまりなかったので、良かったです。
「気付かせてくれた、大切な事」(岡山県・高校2年生)
生きていることと生きること~遺伝子の世界と脳の世界~
独立行政法人 産業技術総合研究所 セルエンジニアリング研究部門
キャンプを終え、一番心に深く残っている言葉があります。初日に行ったニワトリ胚の観察のとき、好きにいじって良いと言われた私は本当に好き勝手に、少しも躊躇することなく、手当たりしだいにバラしました。胚は原形をとどめない程にぐちゃぐちゃになってしまいましたが、私はそれに対し別段何も感じなかったのです。そして翌日の朝、田口先生が私達に言いました。「実験のために犠牲にしてしまう動物達に対し、感謝の気持ちと哀悼の気持ちを忘れてはならない。命は大切にしなさい」と。私は衝撃を受けました。私は何てことをしてしまったのかと。ニワトリ胚に感謝をしなかったばかりか、すまないと思うことさえしませんでした。ただバラバラにすることを楽しんでいただけではないか、と。
これから先、理系の道を進んでいくと必ず動物を犠牲とした実験と再び巡り会うことでしょう。それは時に、今回のような命を奪わざるをえないものもあるでしょう。ですがそんな時、私はあの田口先生の言葉を思い出し、無責任に命を殺めることだけはしまいと誓います。
あの言葉はよく聞くような言葉でしたが、実際の研究者の方が言うからこそ心を打ったのだと思います。そして今度は私が、次の世代へと、キレイ事でも何でもない確かな重みを持ったあの言葉を言い続けたいと思います。大切な事を気付かせてくれたこのキャンプに、心から感謝しています。