| 森林は、木材やその他の資源を供給する機能だけでなく、国土を保全する機能、水源を涵養する機能、生物の多様性を保全する機能、さらには地球の温暖化を防止する機能など、私たちが快適な暮らしを送るのに欠かせない数多くの機能を有しています。かけがえのないこの森林を維持するために、私たち一人一人は「森を知り、森を守り、森を活かす」ことを常に心に抱き続ける必要があります。
森林総合研究所は、森林・林業・木材産業にかかわる中核的な研究機関として、森や樹木をめぐる様々な研究を総合的に行っています。今回のサイエンスキャンプでは、「森の中の多様な植物たちを訪ねる」、「昆虫のフェロモンの不思議を探る」、「木の良さと使い方を知る」の三コースを用意しました。私たちの研究所でのサイエンスキャンプを通じて”森や森の恵み“を学んでみませんか。
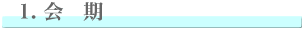
2003年8月6日(水)午後1時〜8日(金)午後3時
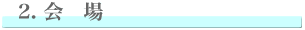
森林総合研究所
〒305-8687 茨城県つくば市松の里1
(東京駅から約1時間30分)
TEL:029-873-3211 内線227
(連絡先:企画調整部研究情報科広報係)
FAX:029-874-8507
URL:http://www.ffpri.affrc.go.jp/
宿泊場所:農林水産省農林水産技術会議事務局
筑波事務所 国内研修生宿泊施設
 |