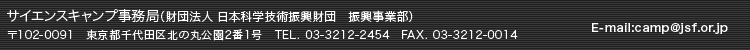「1つずつこなしていく達成感」(広島県・高校2年生)
バーチャルリアリティを活用した3次元可視化・触感の理科実験
埼玉工業大学情報基盤センター
私が今回このキャンプに参加した理由は、将来の進路選択や自分の興味、関心がどのくらいなのかについて明確にしたかったからです。後日、参加が認められた時はとても嬉しかったです。
そして、実際にいろいろな実験をしながら、仲間達との交流を深めたり、大学の先生やTAの人々の優しい人柄や技術のレベルの高さを感じたりすることができました。実験では積極的に取り組み、充実した内容の詰まった日々を送ることができました。大学では2日目にCAVEという物を3次元にして映し出す装置を使いました。3日目になるにつれ、今までに体験できなかったことをすることで物の見方や考え方が変わったように思います。難しい課題もありましたが、1つずつこなしていく達成感はなんとも言えない感動でした。最終日は天候の都合で納得いくまで結果を残すことはできませんでしたが、この3日間の経験はなにものにも変えがたい大切なものとなりました。
私は今までこれだけ1つの分野について深く考え、いろいろな試行錯誤を繰り返したことはありませんでした。この大学での経験は必ず進路選択に役立つと信じ、将来自分の興味が仕事となるよう努力していきたいです。
「将来の目標の発見」(北海道・高校3年生)
自然の贈り物~野草から薬ができるまで~
国立大学法人 千葉大学 環境健康フィールド科学センター
サイエンスキャンプでは、主に漢方について学びました。漢方は同じ病気や症状に対しても患者さんの体質の違いに応じて、さまざまな漢方薬を処方します。西洋医学的視点では疾患部分しかみないのに対し、漢方医学的視点では広い視野で気血水の状態から患者さんと一緒に治療していくのです。漢方は治療だけでなく予防も重視していて、西洋医薬と漢方、更には針灸が個々の特長を出しながらお互いをカバーし合えていくのが理想の医療の形だと私は思います。
講義の中に「良薬口に苦し」というもので、お腹が痛い時に飲む「正露丸」の主たる成分のオウバクとカンゾウを食べました。先生のよく言っていた「ベロセンサー」で感じてみるとオウバクはとても苦く、カンゾウは食べたらちょっと甘みがあり、さすがカンゾウは漢字で「甘草」と書くだけあると思いました。次に日本の3大民間薬の1つであるセンブリを食しました。あの口に残る苦さはもう忘れることはできないと思います。
私はこの先薬科大学へ進学し、西洋医学の利点、漢方医学の利点を患者さんに伝えられる薬剤師になりたいです。また薬学においての予防医療のあり方を更に意欲的に知りたいとも考えるようになりました。ありがとうございました。
「音をあやつっちゃいました」(東京都・高校2年生)
音をあやつる
東京工科大学 メディア学部
私にとって、今回で2回目のサイエンスキャンプでした。1番印象に残っているのは、2日目の午後から3日目にかけて実習したオリジナル作品制作です。私は木管楽器のフルート、オーボエ、クラリネット、サックス、バスクラリネット、ファゴットの音をMIDIからMATLABに取り込んでスペクトログラムにして倍音比較をしました。同じ木管楽器でも音が違って聞こえる理由を見て感じる事ができてとても嬉しかったし、おもしろかったです。
そして、そのスペクトログラムを読み取って音にするということもしてみました。MIDIから取り込んだ電子音なので、自分で作った楽器の音も電子音みたいな音でした。本物の楽器の音を取り込んで作るとちゃんと本物の音になるそうです。どうしたら本物の音みたいになるのかということは卒業研究のレベルだそうです。私は時間も技術のないので、そこまでやってみたかったけれども、できなくて残念でした。
この『音をあやつる』に参加したことによって、音楽に対するみかたが変わったような気がします。部活でフルートとオーボエの音程があまり合わないのも納得できました。このサイエンスキャンプに参加することができて本当によかったです。
「日常生活の中にあるひらめき」(茨城県・高校2年生)
ユビキタスを体験する~ICタグと暮らしへの応用~
東京工科大学 コンピュータサイエンス学部
私がこのサマー・サイエンスキャンプに参加して思ったことは、“研究”というものは難しいものではなく、私たちがいかに便利で、いかに速く、いかに効率良く、いかに安くて安心な日常生活を送るかという科学的探究である、ということだ。そのための知恵か知識というものはとてつもなく膨大な量を必要とし、また、机上だけではなく、ちゃんとシミュレーションもしなければならない。しかし、根底にあるひらめきやアイディアというものは、日常生活の中にある。
サイエンスキャンプ1日目は、RFIDの特徴やしくみについて勉強した。RFIDというのは簡単に言えば、個々に付けられた識別用の数字である。2日目に、そのRFIDがどのような使われ方をしていて、どう利用されているかを学んだ。3日目にRFIDの応用方法についての討論をした。それは、夢のようなアイディアから、現実的な発想と幅広い考えが交わされた。その、1つ1つのひらめきには、全て日常生活と深い関わりがあった。
私はこのサマー・サイエンスキャンプを通して、日々の生活から私たちがどのように支えられて生きているのかと、科学的に考えるということを学んだ。これからは、科学的考えを活かした生き方をしていきたい。
「尽きない疑問」(宮城県・中等教育学校6年生)
生物が見る世界~いくつもの目といくつもの世界~
国立大学法人 浜松医科大学 医学部
高校生活最後の夏の終わりに、私は浜松で素晴らしく魅力的な科学者の方々、優しく丁寧に答えまで導いてくれる大学生の方々、そしてトノサマガエル10数匹と感動的な2泊3日を過ごさせて頂きました。
実習に入ってまず、ディスカッション。班の仲間からたくさん出てくる自分で考えていても出てこないであろう発想にその場で触れられ、そこからまた何かを発想し、実験でその発想を試す。この過程がとても楽しくて、幸せな時間でした。
サイエンスキャンプに来て2日目、今回の体験のメインとなる実験が始まりました。トノサマガエルの眼の連続切片を用い、網膜の厚さを調べます。これはトノサマガエルの行動の原因、理由となっているものを考察するためです。実験の結果をまとめ、ディスカッション。行動の理由を考察します。
キャンプ3日目、トノサマガエルの形態と行動を調べた私達1班は、カエルの網膜が大きいカエルの方が厚いのは、捕食被食の関係や生育が関係しているのではないかと発表しました。2班、3班はカエルを解剖しての実験だったので興味津々に聞かせて頂き、質問をして答えて頂き、それでもまだ尽きない疑問に喜びを感じました。「科学は楽しむ」と最初の講義で先生がおっしゃっていたのですが、全くその通りだと思います。今回そのことに気づかせてくれたサマー・サイエンスキャンプ、そこで出会った素晴らしい人々に感謝の気持ちを伝えたいです。
「単純な動作と複雑なプログラム」(宮城県・高校1年生)
マイクロ2足歩行ロボットの製作と制御
国立大学法人 名古屋大学大学院 工学研究科 マイクロ・ナノシステム工学専攻
今回のキャンプに参加し、僕は有意義な時間を過ごすことができました。中でも印象に残ったことは、ロボットを制御するプログラミングの作成でした。C言語を使うのは、初めてだったので、まっすぐにロボットを立たせるだけでも苦戦してしまいました。しかし、大学生の方にコツを教えてもらったり、自分なりに、命令文を書き加えたりすることにより、なんとか歩かせることができました。方向転換などの、より高度なものを作成して、ロボットにプログラミングをしても、うまく作動しないことがほとんどでした。そういったときは、プログラミングの不備やロボットの回路をチェックしました。これが最も難解な作業でした。それと同時に、原因を1つ1つ突き詰めていき、最終的に、うまくいったときの喜びは格別なものでした。実験や製作を通じて、僕は、単純そうに見える動きでも、意外と多くのプログラムが必要であることに驚きました。C言語は、僕にとっては、まだまだ難しいからこそ、もっと深く学んでみたいという意欲が湧きました。そのためには、まず、学校での勉強をがんばらなければならないと思いました。C言語の表記は英語でもありますし、また、回路図を理解するためには、これからもっと理科や数学の勉強に励まなければならないことを実感しました。
「没頭したロボット作り」(神奈川県・高校2年生)
積み木でロボットを作ろう!
同志社大学 理工学部 インテリジェント情報工学科
キャンプ初日から自由にロボットを作って良いと言われたので一瞬戸惑ったが、私達はボールを追いかけるロボットを作ろうと思いついた。しかし、途中から「追いかけるだけではつまらない。せっかく発表会をするのだから、他に工夫して、見ていて面白いものにしたい。」と考え始めた。その結果、出来上がったのが“ピタゴラスイッチ”のような、なんとも奇妙な装置とそれを動かすロボットであった。
ロボットの外形作りは比較的単純な作業だったが、中身は複雑だ。ロボットは書かれたプログラム通りに正確に動いてくれるという優れものだが、人間がロボットに求める動きは単純ではない。それは、単純な動きを幾重にも重ねた非常に複雑な動作である場合が多いからだ。だから、いくつもの動作を同時にプログラムして、複雑な動きを作り出さなければいけない。ただ、ロボットには書き忘れた部分があっても補ってくれる能力はない。そのため、自分の思っていたとおりにロボットが動いてくれた時はすごく嬉しかった。
作業をしていた2日間は熱中していて、本当にあっという間だった。実際に研究者が作っている、実用化に向けたロボットは一体どれくらいの月日がかかるのだろう、と疑問に思った。このキャンプは、理系に進もうと思っている私の意志を再確認できるものだった。キャンプ中はロボット作りに没頭していた。やはり自分の構想が実現し、上手くいったときの達成感は何物にも変えがたい、と思った。
「お金で買えない経験」(徳島県・高校3年生)
量子世界の探検~超伝導を体験しよう~
国立大学法人 岡山大学大学院 自然科学研究科
この3日間のキャンプでは、あまり超伝導について詳しくない自分でも、理解しやすく説明がされました。そして、そのなかでも、普通に生活していたら経験できないことがいくつもありました。それらの経験は心にとても強く残っています。
その1つは、自分の手で超伝導物質を作って最終日に、本当に極低温で浮くのか実験を行ったことや、抵抗値や超電導になる温度を測ったことです。試料を作って焼き上げている時間は、成功するのかどうかの不安と成功するという自信とが混ざっていましたが、成功したときはほっとしました。そして、成功した後、自分の手で作った超伝導物質が浮いたときには、今までで1番感動しました。また、自分の手で実験を行ったときは楽しすぎて作業にのめり込んでいました。
大学の先生や先輩との交流会も経験の内の1つです。最前線にいる先生方と深い話や今までに持っていた質問を聞くことができ、高校生向け以上に詳しく教えてもらいました。また、サイエンスキャンプは実験や科学のことも大切ですが、全国の人たちとふれあうこともこのキャンプの楽しみだと思います。もしかしたら、キャンプで友達になった人と大学に入った時に、出会うかもしれません。
こんな経験をできる場をくれたことにとても感謝しています。
「未知への興味を刺激した2つの実験」(東京都・高校2年生)
先端科学で地球環境を探る~海洋コアと遺伝子資源~
国立大学法人 高知大学 海洋コア総合研究センター/総合研究センター
“遺伝子資源”“アデニン(A)”“グアニン(G)”“シトシン(C)”“RNA”“コドン”…(etc)どれも聞いたこと事もなければ、見た事もないような単語でした。最初の講義で、こんな単語がいくつも出てきました。初めは、知らない単語が出てくる度に溜息をつきたくなるような気持ちにかられましたが、大学教授の懇切丁寧な説明のおかげで、おおよその事が分かり始めると、もう少し理解したいという思いが生まれました。そしてそれは講義の後の実習・実験によって、より強いものとなりました。
実験というのは、採集した細菌の塩基配列を調べ同定するというものでした。平たく言えば、名前あてゲームです。まずは採集した細菌を培養し、次にその細菌のDNAをPCRを使い増やしていきます。そして、増やしたDNAを染色し、シークエンセーでプログラム化。さらにそれを、ネット経由のデータベースで同定しました。また、それに並行して細菌そのものを染色し、観察する事もしました。
これらの2つの実験は、僕の知らない事への興味を大変刺激してくれました。僕は、新しい知識と感動、そして知らない事への興味を与えてくれた、高知大学のみなさんと、このサイエンスキャンプという企画をしている事務局のみなさんに、深く感謝します。いつかこの思いを、科学者となって、以前の僕のような人を変える事で、お返ししたいと思っています。
「初めて農学を学んでみて」(神奈川県・高校3年生)
農楽体験~自然を知る、食を知る、生物を知る~
国立大学法人 高知大学 農学部(NPO法人高知サイエンスヴィレッジ)
「医学は人を救えるのに対し、農学は人類を救える学問」、その言葉を聞いた時、初めて農学の重要性というものに気がついた。キャンプに参加するまでは農学が具体的にどうような学問であるのかも分からなかったが、参加後には、現在地球がむかえようとしている危機を解決するには農学の力が必要だと確信するようになった。
キャンプに参加した目的は2つ。1つは環境に興味があり、農学をやれば環境についても学べると思ったからだ。もう1つは農作業を体験してみたいという理由だ。
キャンプで1番強く印象に残ったこと。それは農学は深く将来を見据えた学問であるということだ。地球の人口が増え続けるなか、食糧確保は人類滅亡の危機を救えるかどうかの鍵となる。その食糧確保を可能にするために農学は研究し続けられているのだ。その研究は遺伝子組換えという最先端の技術から、化学農薬に頼らないで害虫を減らすための益虫の増殖に関する研究まで、とにかく多種多様であった。農学とは人間が自然と1番深く接する場である。そのため人間が農業をコントロールしようとすることにはかなりの困難が伴う。しかしその困難を乗り越え、人間と自然がうまく共存できるようにする学問が農学ではないか。
実習では農作業を初めて体験した。カマを使い、コツをつかむのに苦労した稲刈りや、たくさんの実をバッサリと切り落としてしまう摘果作業など、想像とはまったく異なっていて驚きの連続であったが、新鮮な体験でもあった。
貴重な時間を作ってくださった皆様、参加した仲間、本当にお世話になりました。
「それでも獣医師になりたい!」(鹿児島県・高校1年生)
哺乳類の発生工学~卵子と精子の出会いと発生~
国立大学法人 鹿児島大学 農学部 獣医学科 附属動物病院
私はこのキャンプに参加するまで、牛の精子と卵子の体外受精といったら、取り出してある卵子の1つに精子1匹を顕微鏡で見ながら入れて終わり…というようなものだと思っていました。しかし実際は、まず牛の卵巣から卵子を取り出すところから始まるとても大変な作業でした。しかも顕微鏡でなら簡単に見えると思っていた卵子は小さすぎて見つけるのも困難だったり、精子の濃度を計算して調整したりと、今まで考えてもみなかったことの連続でした。でもその1つ1つが驚きと感動でいっぱいでした。
動物病院の診察がどんな風に行われているのか知らなかったのですが、院長先生のお話を聞いて、改めて獣医師になることの大変さを感じました。獣医師であっても、ただ動物に接していればよいというものではなく、飼い主さんと患畜の様子を見て、話を聞き検査結果などから総合的に判断するそうです。時には飼い主さんの勘違いを指摘することもあるそうで、人間とのコミュニケーション能力も必要だと感じました。
1番印象に残ったのは受精卵を牛の胎内に入れる場面で、獣医師になる決意がこんなに揺らぐのは初めてでした。でも現実にはもっと多くの壁があるはずです。この経験を活かしていい獣医師になりたいと思えた夏でした。
「顕微鏡の中の感動の世界」(石川県・高等専門学校2年生)
形が語るミクロのストーリー
国立大学法人 北陸先端科学技術大学院大学 マテリアルサイエンス研究科
「感動」、それはとてもすばらしいものだと思いました。
顕微鏡は、私たちが普段見えない未知な世界を見せてくれました。その顕微鏡の中に見える世界はとても想像では考えられないものであり、自分の想像を超えるものでした。光学顕微鏡では生物や無生物の違いを見比べ、また卵から生まれる魚の過程を追うことによって大きな感動が得られました。透過電子顕微鏡では原子を真空中に飛ばし、結晶を見ました。見る場所によって、色や線の太さなど、多くの違いを発見することができました。原子がきれいにならんでいることに驚き、強く感動しました。原子間力顕微鏡では、ポリマーを見つけるのに3時間近くかかり、とても大変な作業でした。でも、それらしき物を見つけた時の感動はすごかったです。普段の高校生活ではできないような高価な顕微鏡を、1から10まで操作を教えてもらいました。操作は顕微鏡によって大きく異なりとても難しかったけれど、物が見えたときの感動はとても大きかったです。
このサイエンスキャンプに参加して、感動すること、そして不思議に思うことの大切さを実感しました。ありがとうございました。
「動物行動学っておもしろい!」(大阪府・高校2年生)
多様性の海へ~マリン・エコロジーへの招待~
南三陸町自然環境活用センター
私は今回、このプログラムの中にあった「動物行動学」という言葉に引かれ、南三陸町のサイエンスキャンプに応募し、参加しました。
私が期待を寄せていた動物行動学実習では、ヒメイカの摂食行動観察と最適摂餌戦略実験を行いました。実験内容は「ヒメイカは大きな餌と小さな餌が同時に現れたとき、どちらを選ぶのか?」というもので、餌には、ヨコエビというとても小さなエビを使いました。観察中に見たヒメイカのヨコエビの食べ方には、驚きました。ビークという歯を使って、エビの殻を上手くこじ開けて身を食べるところを見ると、ヒメイカも小さいけれど生きているということを感じました。また、仮説を立てて実験することが、新鮮なことでした。学校の実験ではない、時間をかけて、話し合って仮説を立て、それから実験をしてみるということが楽しかったです。仮説と実験結果が異なったときには、なぜ違ったのかと考えていくところも、実験をする楽しさだと分かりました。また、そんな時には、講義で終わった「動物の目線に立って考える」ということの大切さも知りました。今回の実習で、気持ちを知ることができない動物の行動を解明していく動物行動学にさらに興味を持ちました。
このような企画に、これからも積極的に挑戦していきたいと思います。
「脳科学へのいざない」(東京都・高校1年生)
未来へつながる最新の情報通信技術を研究しよう!
独立行政法人 情報通信研究機構 神戸研究所 未来ICT研究センター
情報通信の研究をしているNiCTになぜ脳の研究所があるのか。最初は少し疑問だったが、脳内の情報伝達の仕組みを、人間が作り出した情報通信に役立てることができるかもしれない、というように、脳の研究が通信に密接に関わりあっているのだとわかった。同時に自分の脳の中に素晴らしい情報伝達のしくみがあることを再確認した。
私達の体全体の司令塔である脳は、最も身近なところで常に活動している。しかし、最も身近でありながら自分の目でその活動の様子を見ることはできない。だから、MRIのような、脳の活動を手術もなしに測定できるという画期的な機械に感動した。そして、実際にMRIの画像を解析し、脳内の活動場所が立体的な模型の画像に映し出されたときの興奮は、今でも忘れられないほど貴重な経験となった。
今NiCTの脳情報プロジェクトでは、言葉で伝えきれないことを脳活動のパターンから読み解き、意図をより的確に相手に伝える研究をしているそうだ。それは少し味気ない気もするけれど、私も将来、脳科学を何らかの形で生活に生かしていくようなことがしたい、と強く思った。脳の魅力を感じ、将来について考える一歩となった貴重な3日間だった。
「出会いと発見」(東京都・高校2年生)
いろいろな物質・材料に触れてみよう
独立行政法人 物質・材料研究機構
私は高校で学習する範囲を越えて理科に触れてみたいという気持ちで今回のサイエンスキャンプに参加し、このキャンプの中で様々な発見をしました。
1つは物質・材料の研究が私たちの生活においてどれほど大切であるかということです。かの有名なタイタニック号が沈没した原因の1つは、ある温度以下で脆くなる「低温脆性」という金属の性質が関連しています。もしタイタニック号の船体に低温でもねばり強い材料が使われていたら、船は沈没しなかったかもしれません。また私たちの身の回りの中でも、電車のレールには温度変化や摩擦にも耐えうる材料が使われ、包丁にはさびにくいようにステンレスがよく使われています。私達の安全な暮らしは学者の地道な研究の上に成り立っていることを知りました。そして、科学の研究は、研究のためではなく社会のためにあるということを実感しました。
また、もう1つの発見は研究者の方々が何事に対しても誠実に取り組むということです。実験や講義の際はもちろん、活動発表の準備の間、私達の質問に1つずつ丁寧に答えて下さったことをよく覚えています。このようなスタンスが研究の基盤となっているのだと感じました。この2日間は大切な思い出となりました。そして思い出にとどまらず、これから進路を考えるきっかけにしていたいと思います。
「サマー・サイエンスキャンプに参加して」(福島県・高校1年生)
自然災害が発生するメカニズムを学ぼう
独立行政法人 防災科学技術研究所
私がサイエンスキャンプに参加しようと思ったきっかけは、学校の部活動の先輩の紹介でした。私は防災科学技術研究所に参加しましたが、そこで見たもののほとんどは、それまでの15年間の人生の中で初めて目にするものばかりでした。
私が最も感銘を受けたのは、雪崩の実験です。私が住んでいる町は太平洋に近い所にあり、1年を通して比較的温暖な為、冬でもほとんど雪が降らず、降ったとしてもせいぜい数ミリ程度しか積もりません。なので、雪崩など無縁だと思っていたのですが、決してそんなことはないのだということを知って、とても驚きました。そして地盤液状化についても、今までテレビや新聞などで見たことはありましたが、ペットボトルに水・砂という極めて身近なものだけで再現できる、ということにも大きな感慨を抱きました。これら以外にも地震や火山、竜巻など充実した内容のものばかりでした。
今回参加したサイエンスキャンプは、見るもの全てが非常に新鮮な感じがしました。この時経験したものは、広い意味で今後の私の人生に非常に大きなプラスの影響を与えてくれたと思います。最近では大きな自然災害が頻発しており、いつ自分の身に降りかかってくるか分かりませんが、そんな状況に陥ったときでも、今回身につけた知識さえあれば、これほど心強いものはないと思います。
「再生医療の発展」(兵庫県・高校2年生)
理研の最新研究成果を体験しよう!!
独立行政法人 理化学研究所
僕は今回、理化学研究所での再生医療に関するコースを選択しました。再生医療というのは、人間本来の自己治療能力を活性化させることによる治療であり、患者の細胞を使って、新しい臓器を作ることが最終目的とされています。
今回のサイエンスキャンプでは、その再生医療研究の一端として、ES細胞と間葉系幹細胞の培養及びパターニングを行いました。細胞のパターニングとは、再生医療における基礎、細胞を操作する“手”にあたる技術です。目的の組織を作る上で、細胞の並び方を操作することから始まるわけですから、パターニングは再生医療の基礎であり、それ故に最も重要な技術であると思います。
あと、同年代の、同じようなことに興味を持つ人達と会話できたのは貴重な体験でした。また、理化学研究所の理事長とお話しすることができました。その中でも心に残っているのは、“問題を解くことは、すでに決まっている答えを導き出すことだが、研究はあるかどうかわからない答えを探すことで、単に難しい問題を解くのより、遥かに難しい”という言葉です。改めて理事長は凄い人だと思いました。
僕は前々から遺伝子工学に興味があり、将来はそれに関係した職業に就きたいと思っていましたが、このキャンプを終えて、さらにその思いが強くなりました。この体験を今後の人生の糧としてゆこうと思います。
「強大な爆弾に火がついた…」(福島県・高校2年生)
宇宙開発・宇宙科学の最前線を探る
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター
見事に、私は改めて宇宙にどっぷりと填りました。そして、かなり刺激を受けたため、通常の日常生活に戻った途端、この3日間とのギャップに愕然としました。そのため、一瞬自分を見失いかけて、勉強も手付かずで、蛻殻状態でした。
夢の様に楽しかった3日間の記憶に浸り続けて2日目のこと。夜の8時頃に夜空をいつものように見上げていました。しかし、以前とは見方が変わっていました。1等星はあれかな?人工衛星が分かるかな?あの月には今“かぐや”が探査に行っていて、あのはたらきをしているんだろうな…、と思うようになりました。
そこでふと、人口衛星は約90分で地球の周りを1周するんだよなと思い、人口衛星の速度を計算するには、と頭の中で考えようとすると、なんと頭が全く働かないのです。例えて言うなら、最初は熱湯のように熱かったサイエンスキャンプの思い出が脳を包みこんでいたのに、次第に冷めていき、ぬるま湯が脳を包みこんでいる状態になり、脳の働きが弱まり、甘い事ばかりを考える様になっているのです。このままでは駄目だ!宇宙に携わりたいのなら、変わらなくては!!と思い、頭の中のぬるま湯を抜いてしっかりとして行こうと思いました。
これからはJAXAに入社することを目標にやっていきます。まず第1段階としては、学校でのテストや模試で上位となり、東京工業大学に合格することを目標とします。私は良い夢を持ちました。JAXAに入社して、ロケットのエンジンに携わりたいです。とにかく、目標達成に向けて一直線で頑張ります!この体験は一生の中でも大きな宝となりました。
「未知との遭遇、サイエンスキャンプの3日間」(広島県・高校1年生)
航空宇宙技術の最先端研究を身近に体験してみよう
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 調布航空宇宙センター
3日間で1番印象に残ったことは、「飛行安全技術セミナー」です。最初は資料の中の用語があまり理解できなくて戸惑ったけれど、3つのグループに分かれて資料を解析していくうちに、事故の原因や飛行経路についてだんだんとわかってきました。様々な視点から事故をみて、十分に解析していくことが、2度と同じ事故が起こらないようにする上で大切なことだとわかりました。
また、飛行機を設計していく上で、地球環境への配慮や限りある資源の有効な使い方など、いろいろなことを視野に入れ、考慮していかなければいけないこと、特に、技術面を高めることで安全性が失われる可能性があることを知りました。
この3日間で学んだ内容は、難しくてわからないところも多くありましたが、実験や実際に目で見たり触れたりすることで、少しずつ理解し、興味を深めることができました。そして何より、同じように夢や希望を持つ全国の仲間と共に3日間学べたことが、本当に嬉しかったです。
私は、このサイエンスキャンプに参加して積極的に何かにチャレンジすることで、自分自身の可能性を広げることができると感じました。
あっという間の3日間でしたが、私にとってこの3日間は、かけがえのない貴重な宝物です。これから、この経験を少しでも社会に役立てていくことができるように、頑張りたいです。
「邂逅・キセキ」(岡山県・高校2年生)
あなたも体験未来のロケット技術
独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 角田宇宙センター
僕には夢がある。宇宙に存在するという目に見えないダークエネルギーを見るというものだ。そのためには、宇宙に向かうためのロケットが必要であり、そのロケットのエンジンを研究している角田宇宙センターに行きたいというのが、思えば、今回の応募理由だった。
しかし、実際にふたを開けてみると、当初掲げていた目標など、忘れてしまうほどの濃い内容をもったサイエンスキャンプとなった。内容のすばらしさはもちろんのことながら、自分と同じような夢を持ちながらも、普段の学校生活を営むうえでは、決して出会うことのなかったはずである、青森・宮城・福島・茨城・神奈川・兵庫・広島・そして岡山の8県から来た、学校が違えば、学年も違うメンバーと出会えたことは、なにものにも代えがたい『奇跡』であると同時に、おもしろいことだと思う。それぞれのメンバーは、自分の学校生活などの中にはっきりした『軌跡』を持っていて、その『軌跡』が重なって、こうして『邂逅』を迎えることができたことは本当にうれしかった。
セミナーの内容は、予備知識がいくらかあったおかげで、とても楽しかった。学校で補習を受けるのはつらいけれど、サイエンスキャンプで受けたセミナーは苦にならなかった。むしろ学校の補習よりもセミナーのほうが、自分が強い興味を抱いている分、とっつきやすかった。講師の先生方の話し方も面白く、いっそのこと、学校で先生をやってくれればいいと本気で思った。でも、それは無理な相談だろうから、近くで講演会を開いてくだされば、必ず参加したいと思う。もちろん、サイエンスキャンプにもまた参加したい。
「将来への第一歩」(神奈川県・高校1年生)
海洋~地球環境変動の鍵をにぎる世界~
独立行政法人 海洋研究開発機構
私がキャンプに応募したのは、地球環境を考える上で海という視点は面白い、という漠然とした理由からだった。しかし、実際に参加してみると、今まで自分が頭に描いていた“海”に比べ、本物の海ははるかに奥深く、広大なものだった。
深海の生物はカニなのに真っ白だったり、眼が退化していたり、とユニークで、圧力の高い、まっ暗闇で生きのびるために適応した姿を真に見ることができ、改めて深海の過酷さを感じた。圧力体験では水深30mに相当する圧力を体験し、うちわで空気をあおいだ時には空気が重く感じられ、普段感じることのできない不思議な感覚を味わった。これの何倍もある深海の圧力がどれだけ大きく、深海がどれだけ過酷なものか、身をもって感じられた。特に潜水艦についての講義では、あれだけの圧力に耐えられる潜水艦を作る技術にとても感動した。他にも深海について当たり前だと思っていたことがそうでなかったりと、驚いたり、水の恐ろしさを改めて知ったり、様々な知識も得ることができ、知らないことを知る面白さを感じた。
また、全国から集まった高校生との交流とても楽しいものだった。中には将来の目的意識をハッキリ持っている人もいて、話を聞いて自分にとってプラスになった。
私はサイエンスキャンプに参加して様々なプログラムを通し、今まで自分の視野がいかに狭かったかを痛感したと同時に、キャンプは視野を広げるきっかけとなった。ただ漠然と科学が好きだった私にとって、実際に「生きている」科学を見られたのは、とても大きなことだったと思う。
「『未知』と『既知』の間にあるもの」(埼玉県・高校3年生)
原子力エネルギーや放射線利用の研究開発を体験しよう
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 東海研究開発センター
原子力科学研究所/那珂核融合研究所
今回のサマー・サイエンスキャンプにおいて1番心に残ったのは、「未知」を解消することで得られる視野の広がりだった。原子力という重要かつ未知の部分が多い分野に直接触れることで、今までにないスケールの視野の拡大を実感することができた。特に研究用原子炉や各種原子力施設の見学は、世間一般には関係者以外入れない設備を存分に感じることができ、同時に管理区域へ何度も立ち入るという貴重な体験もすることができた。
また、研究者の方々による座学も非常に興味深く、最前線にいるからこそできる実践的知識と教化的知識の融合は、毎日行われた見学の実感とも合わさって、とても有意義だった。さらに、随所に挟まれた自分主体の実験や最後に行った発表などにより息つく間もなく、常に刺激的だった。
また、全国から集まった同世代の人間との交流もとても新鮮だった。「理系」か「文系」といった基本的な区分けすら通用せず、その日体験した出来事を自分の価値観で分析し、自由に話し合った数日間は、人間としても成長できた日々でもあり、最後の発表に向けた準備では、考えた事を短時間で形にする難しさをも味わった。住む所が違えば考え方も違い、通う学校によっても思考の過程が変わる現実は、発表準備の際に顕著になったものの、それすらも個性としてプラスにしてしまう力が、このサマー・サイエンスキャンプには存在した。
これからは、最先端にどっぷり浸かったこの数日間を糧にし、来たるべき将来や受験に挑んでいきたいと思う。
「未知」を減らし、「既知」を増やしていく探究者としての第一歩を、私はこの夏で確実に踏み出せたと信じている。
「人生でかけがいのない3日間(大阪府・高校2年生)
原子力研究における最先端技術を体験してみよう!
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 大洗研究開発センター
私は参加2回目となりますが、今回は参加する事で受験に対するモチベーションを高めようと思いました。また発展著しい原子力の分野にも魅力を感じたからです。
大洗研究開発センターでは私の想像を超えた研究がされていました。その中でも特に、水に電気を通すことなく、ヨウ素と硫黄を用いて水素を作るISプロセスには心を動かされました。私はこの水素エネルギーによって、今世界中が悩むエネルギー問題が解決されるであろうと確信しています。腐食の実験では、実際に試料に溶液を浸してその侵食度を計算しました。この実験を通じて研究というものの大変さと、あまり知られることのない材料の研究開発が工業を基盤から支えていることを知り、その重要性を実感しました。またそこで実際に働く研究者の方たちと話をすることで、研究に対する姿勢と熱意を学び取ることができました。
今まで原子力については核兵器などの悪いイメージばかりが先行していたのですが、プログラムを通してあらゆる可能性を秘めた魅力のある素晴らしい分野であることがわかりました。また、このキャンプでは全国から集まった仲間たちと出会えました。最初はやはり緊張しましたが、同世代の同じ志を持つ仲間たちとのふれあいは、私に刺激的なものを与えてくれました。仲間たちとの出会いは一生の財産であると思います。3日間という短い間でしたが、ここで経験した多くのものは私の人生でかけがえのないものとなるはずです。今後はこの貴重な体験を是非生かしていきたいと思っています。
「研究者とはなにか」(大阪府・高校3年生)
光科学の魅力に触れる
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 関西光科学研究所
今回、関西光科学所で研究者が普段どのようなことをしているのか、ほんの一部ですが、体験させていただきました。この研究所には巨大なレーザー実験施設があり、特別にそこに入らせていただけることとなりました。いざ入ってみるとそこには巨大なレーザーを中心に大量の機器類があり、その様相に圧倒されるばかりでした。とにかくすごくて、一見してハイテクノロジーを感じさせてくれるような代物でした。また、光科学とは関係ないですが、ドライアイスの製作にはその派手さのために何度やっても飽きることはありませんでした。
しかし研究者はいつだって派手なことをしているわけではありません。むしろそうでないことのほうが多いでしょう。今回のメインの実験「放射性物質の同定」は地道な作業の連続でした。細かいところは研究者の方々が尽力して下さって、僕のところにやってきた実験データはおそらくずいぶんと精製されたものであったことでしょう。それでもやはり数字やグラフと向き合っていると、考えこんでしまうこともしばしばありました。研究者の方々は普段、これよりもずっと膨大で複雑なデータを取り扱っておられるのでしょうから、感服いたすばかりです。
僕は、今回のサイエンスキャンプで最新鋭の見学や派手やかな実験のみならず、研究の根幹をなしているであろう地道な作業をも体験できたことは、とても有意義だったと思っております。この3日間の体験がこれからのいつかに役立つことでしょう。
「感じてみたよ!!地球の姿」(東京都・高校1年生)
感じてみよう!!地球のすがた~地下の世界を探る~
独立行政法人 日本原子力研究開発機構 東濃地科学センター
プログラムの題名と内容に何となく、しかし、激しく魅了され、応募したが、その「直観」は間違っていなかったようだ。
興味がある割には月並の知識しか持ち合わせていなかったため、参加前は不安で一杯だったが、講義の内容は分かりやすく、無遠慮な私の口からポンポンと出る、講義の内容に関係あるのだか無いのだか分からない質問に優しく答えて下さり、一緒に考えて下さった研究者の方々のお陰で、凄く楽しい時間が過ごせた。
今回特に印象に残ったのは、研究者の人柄と、実習で行った空中写真を用いた地形調査だ。研究者の方々は皆優しくて面白くて、何よりやはり博識で、科学者志望の私にとっては正に憧れの人達であった。
また空中写真を用いた実習には、異なる方向から撮った2枚の写真を立体視して、断層が出来ている所を探す、これが実に面白かった。1つ1つの地形をじっくり眺め、それがどのようにして出来たのかを考える作業はとても難しく、1人よがりになってしまうため班で相談をしたが、思いもよらなかった観点であったり考えであったりを共有することができ、協力することの大切さを改めて学んだ。また、簡易実態鏡を覗いていると、行ってもいない写真の中の土地に行ったような気分になり、時を忘れてじいっと見入ってしまっていた。作業としては地道だが、だからこその面白さがあり、研究作業というものの醍醐味を垣間見られた気がする。
他にも地下200mの立坑に入ったり、岩石を観察したり、と濃い3日間だった。私達の暮らす、大きな大きな地球。それは生きており常に躍動している。今回キャンプを通して地球という惑星がより身近に感じられるようになった。
「研究者の方々が支える日本の農業」(栃木県・高校2年生)
農業研究の最前線をのぞき、触れる~病気・害虫~
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 中央農業総合研究センター
初めは見たこともない実験器具や装置に驚き、本当に私は理解できるのだろうかと不安でいっぱいでした。しかし、研究者の方々は私のどんな小さな質問にも丁寧に優しく答えて下さいました。また、実験でいろいろな器具を扱うことができ、本当に感激しました。特に電子顕微鏡の大きさには圧倒されました。ウイルスを観察した時は、日ごろ教科書で見ている感覚との違いを味わえました。また、写真にもとっていいただきました。
1番思い出に残っているのは、「いもち病」の原因となるカビについて学んだことです。東北地方で問題となっている「いもち病」はカビの胞子がイネに付着することにより、イネを「いもち病」に感染させます。そのため抵抗性遺伝子を用いて感染を防いでいます。しかし、遺伝子組換えは行わず、地道に作っていくそうです。私は今まで遺伝子組換えについて悪いイメージを持っていましたが、悪いことでは全くないのだと感じました。地道にやると10年もかかることを、遺伝子組換えではたった1年で出来るのです。同じ内容のことをしているのに、世間の人々はよく知りもしないで判断しているのだと思います。私はもっと遺伝子組換えの安全性について人々に知ってもらいたいと思っています。
このキャンプを通して興味もふくらんだし、考え方も変えることができました。もっとたくさんの人にこのサイエンスキャンプに参加してほしいと思います。
「失敗から学んだこと」(静岡県・高校3年生)
ダイズのDNA、タンパク質、代謝産物を探ろう
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 作物研究所
2泊3日という短い間でしたが、多くのことを学ぶことが出来ました。その中でも、特に覚えているのは、『DNAを探る』です。
DNAを抽出する際に、小葉をしっかり磨り潰されていなかったので、遠心分離にかけたとき、皆とは違う色の2層に分かれたのです。実はしっかり磨り潰せたと思っていた小葉が、細胞壁や細胞膜までしっかり磨り潰せていなかったのです。「失敗しちゃった」と残念に思っていたのですが、研究者の人が、「皆と一緒よりも違うほうが面白いよ」と言ってくれたので、元気が出ました。
抽出したDNAを電気泳動にかけたら、驚くことに、良い結果が出たのです。そして、皆と、ほぼ変わらないような結果だったのです。これには、本当に驚くと共に、嬉しさが込み上げてきました。
私は、この実験から、とても重要なことを学んだ気がします。それは、「失敗をしたからといって、諦めない」ということです。諦めてしまえば、全てがそこで終ってしまいます。それこそ、悲しいと思います。「絶対に、最後まで諦めてはいけない」と思いました。
普段、学校で味わうことができないようなことを、見て、触って、感じて、体験することができ、そして、大切なことを学び、将来の夢に一歩でも近づくことができたと思います。この貴重な体験を無駄にしないように、日々努力し、将来の夢が実現するように、頑張っていきたいです。
「地道な研究が実を結ぶ」(東京都・高校2年生)
果物とのふれあい~果樹研究のおもしろさを体験しよう~
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹研究所
あっという間、でもとっても濃い!そんな充実した3日間だった。“今採った”新鮮な果物は思わず笑顔になってしまう程美味しいし、研究所の方々は私達のことをとてもよく考えて下さるし、一緒に参加した人達とは、初日から夜中まで語り合うような仲間になった。
将来を考え始めた時、生きる上で必要不可欠であり、且つ私達を幸福な気分にさせてくれる“食”に興味を持った矢先のことだった。一番の理由は“おいしくて好きだから!”こうして果樹研を志望した。
講義・実習内容は、今までに触れたことのないことばかりだった。しかしどれも基礎から教えて頂けたのでとても理解しやすかった。特に思ったのは“学校の勉強は大切なのだ!”ということ。例えば品種改良では、生物で習ったメンデルの法則を使い、形や毛の有無、肉質等様々な要素を上手く組み合わせて、よりおいしく育て易い品種を作る。また病害診断ではDNAや酵素、タンパク質の特質をコントロールすることが必要だ。果肉の甘みの増減には、果肉に含まれる成分の化学的性質が関係する。今まで学校の授業で教わってもいまひとつ分からなくて“だから何なの?”という部分が、実際の研究を体験することでよく分かり、授業と生活がつながっているのを感じた。そして学校の授業をもっと頑張ろう、と思えた。
最終日、研究者とのグループ討論はとても有意義だった。自分のやっている研究に誇りを持っており、心から楽しい!と感じながら研究を行っていることを知った。どのような経路で現在の職に就いたのかも一様ではなく、大学の話もおもしろかった。女性研究者から頂いた一言“妥協しない!”は心に響いた。私も将来、楽しい!と感じていられる職につけたら幸せだなぁ!
「研究は精神との闘い」(千葉県・高校2年生)
ハチミツとクローン~豊かな食とやさしい環境をはこぶ畜産の最新研究を学ぶ~
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 畜産草地研究所
3日間に渡るキャンプで思ったことは、研究や実験は知識ももちろん必要だけれど、それ以上に根気が重要になってくるということです。
特にそれを顕著に感じたのは、牛の超音波診断装置による妊娠診断を見学した時です。機械を牛の子宮内へ入れたまでは良かったのですが、なかなか胎児が姿を見せてくれずに、小1時間くらい装置の画面とにらめっこしていました。しかし、その分、胎児の影が映ったときの内なる喜びはひとしおでした。生物相手だと思い通りに事が運べないということに、我が身をもって経験したよい機会になりました。
また、牛の給与飼料を設計する際にあたってパソコンのソフトを用いるのですが、とにかく難しかったです。飼料には粗飼料と濃厚飼料とがあって、粗飼料は繊維が多く含まれ安あがり、一方、濃厚飼料は栄養価が高く、牛乳の質も良くなるという特徴があります。2種類の飼料の量、栄養バランスを考えつつ設計しようとしても2つの栄養が不足してしまったり、はたまた必要以上にあげてしまったりと苦戦しました。研究所の方々は毎回この何億通りも組み合わせの見つかる作業を勘と経験を頼りにしているのかと思うと、やはり一筋縄には行かないのだと改めて学びました。と同時に、研究の醍醐味は地道にコツコツ調べていくことだとも考えました。
他にも微生物の持つ能力に驚かされたりするなど、本当に得るものが多くありました。サイエンスキャンプをきっかけに農学に関する視野がまた少し広がったと感じています。
「『生物』という偉大な先生」(岩手県・高校2年生)
動物を衛(まも)る ヒトを衛(まも)る
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 動物衛生研究所
今回のキャンプは本当に短いものでした。何から何まで初めて経験することばかりで、自分はこの3日間やっていけるのかと不安に思う一方、参加するからには自ら学ぼうという思いで、このキャンプに参加しました。
キャンプ初日からマウスの解剖、家畜の臨床検査、毒薬を用いた検査、顕微鏡での病原体観察など、自分の身体全てで感じるものでした。でも観察以外でもたくさんのことを学びました。例えば、1つの命の重さ、動物の気持ち、病気と生物の欠くことのできない関係…という、実験をしたから自分が学べたことが多くありました。これらを感じたからこそ3日間を充実して過ごせたのだと思います。珍しいものも多くて、生きている病原体や日本初のBSE、学校では見ることができない高度顕微鏡、大腸菌のリアルな写真までも見ることができました。やはり1番の印象といえば、牛の直腸検査です。牛の体温は高いので体内は当然温かかったです。でも、今自分が何を触っているのかというのは分からず、手探り状態でした。私達が直腸を悪戦苦闘しながらやっている間、牛もつらかったのに我慢して耐えていてくれたことに感謝です。
「成長した3日間」(埼玉県・高校2年生)
水と土を活かした研究~水資源、水の浄化、魚のDNA~
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農村工学研究所
私は、今回このプログラムで水環境について詳しく知ることができました。初日のセッションⅠでは、川の流れている場所に行き、川の流れる速さを調べて、川の断面積量を求めました。高校生で習ったばかりの数学の知識や物理が関係して、難しかったけれど、研究員の方々が丁寧に教えてくださり、また、同じ班の人と力を合わせて答えを出すことができました。
セッションⅡでは、水質実験を行い、3つのテーマから自分のやりたいものを選びました。私は、重金属について調べ、重金属が水質作物にどのような害を与えるのかを考えました。私達が取り扱った重金属は、亜鉛で、学校の授業でもよく耳にする物質だったので、実験内容に関しては親しみやすいものでした。実験が終わり、最後は全員でまとめを行い、発表しました。研究員の方やグループの人たちと、分かった点や不思議な点を述べて1つの結論にたどり着くことが出来て、とても充実した実験となりました。
最後のセッションⅢでは、ドジョウのDNAを抽出し、産地鑑定をしました。DNAが目で確認できた時、みんなで驚きました。DNAの産地鑑定については少し難しい点がありましたが、あきらめず資料などを使って分析しました。仮に間違ったとしても、恥じることはなく反省点を冷静に見つめなおせました。
今回のキャンプは、色々な人との交流で視野が広がり、成長した2泊3日であったと思います。また人前での発表によっても自分に自信をもつことができたと思います。
「憧れ増した、夏の旅」(愛媛県・中等教育学校6年生)
気候温暖化や冷害などの気象変動に対する技術開発の研究現場を体験しよう
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 東北農業研究センター
初めて東北の地に足を踏み入れたその日、私にとって最高の3日間になるような気がしていました。
広い敷地、温かな人柄の職員の方々、そして楽しい仲間達。このような環境で学べることに深く感謝したのを覚えています。作業着を着て田へ入り、山を歩いて虫を捕まえたことが私には衝撃でした。なぜなら、研究者と体力は私の中は結びつかない言葉だったからです。汗をたくさんかいて、足を痛くしながら行った体験は、私の描いていた研究者像を打ち砕きました。しかし、決して不快なものではありませんでした。元々、動きまわるのが好きな性格でしたので、体を動かす“研究”をさせていただいたことで、研究職への憧れは更に強まっていきました。
体を動かすことだけかというと、そんな訳はなく、世界に2つしかないという実験施設は流石でした。環境設定されたビニールハウスや機械で生育をコントロールするシステムなど、大変興味を持ちました。まだ、難しい理論は分かりませんが、これから学んでいく分野なのだと思うとワクワクしました。分からないことが多くあるのは、勉強できることがまだたくさん残っているということなので、今から学んでいけることが楽しみです。
愛媛に帰ってきてから、県の農業についても調べてみますと、県の特産品のみかんにも温暖化によって皮が剥がれる被害が起きていることを知りました。農業がなくては人々は生きていけません。東北農研で学んだ、これからの地球の農業のあり方を、今一度考えてみなければと思いました。
「サツマイモに感謝」(静岡県・高校1年生)
サツマイモを知ろう~品種開発から栽培・利用まで~
独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 九州沖縄農業研究センター
私はこのキャンプで、沢山の事に感動し、息をのみました。その中でも特に心に残ったのは、参加前から興味を持っていたアントシアニンを抽出し、pHを調整して変化させた色です。教科書に載っているほど鮮やかではなかったけれど、1から自分で行ったので、私の心にはどの写真よりも鮮明に残っています。アントシアニンが酸で赤くなり、アルカリで黄色くなるという事を私は絶対に忘れないと思います。化学の魅力を再確認することができ、化学が以前よりもずっと好きになりました。
一緒に参加した8人の仲間達は学年も、住んでいる所も全然違ったけれど、会えて本当に良かったです。サイエンスキャンプに参加していなかったら絶対に出会えなかったと思うし、共に実験をし、講義を聴き、意見を出し合って発表の準備をしたことは最高の思い出になりました。
沢山のことを教えて下さった先生方とも交流会でお話をさせていただき、思っていたよりもずっとアットホームで、楽しい研究所なのだと思いました。参加する前は、将来研究者になるのは暗いイメージがあって嫌だと思っていたけれど、研究者になるのもいいかなと思いました。
講義の内容は学校の授業とは比べ物にならないほど難易度が高く、専門的で、サイエンスキャンプに参加しなければ教わることができなかったと思います。この3日間は私にとってかけがえのない3日間でした。私はこの3日間を忘れません。
「最高の思い出」(青森県・高校2年生)
未来につなげよう 安全な農業と環境
独立行政法人 農業環境技術研究所
同じ分野に興味を持った高校生が全国から集まって過ごしたこの3日間。私はきっとここで感じた感動、そして出会いを一生忘れることはないと思います。
1日目の講義では、普段あまり深く考えたことがない「土」について説明を受け、土は地球にしか存在しない天然資源だということを初めて知りました。他の惑星にはなく、地球にだけあるということは奇跡としか言いようがないと思います。それと土は、無生物界と生物界を結ぶ大きな橋として地球上の陸上生態系を支えています。したがって、「土」は、岩石・気候・生物・地形の間に生じる複雑な相互作用の進化過程によって地表に生成した歴史的自然体であり、土壌によって構成されている地表の領域は「土壌圏」と呼ばれているそうです。
研究者との交流会ではいろいろな専門的分野の方々と話し合いができてとても嬉しかったです。研究者の方々は自分の研究を楽しそうに話してくれて、本当に研究が大好きなのだと、私も楽しく話を聞かせてもらいました。研究者の方々との話し合いで印象深かったのは、出身地が同じ研究者の方がいて、学校や勉強の話で盛り上がりました。私は今、勉強していることがすべて社会に出て役立つとは思えず、聞いてみました。すると研究者の方は「確かにすべてが役に立つとは言えないが、研究をしていて行き詰ったときに発想の手懸りとなってくれる。」と答えてくれました。豊富な知識があることによって問題を解決するのに様々なことをしてみて、そこから新たな発見が生まれると聞きました。このキャンプに参加しなければ出会えなかった人々。みんなとの別れは本当にさみしかったけれど、同じ夢を持っている限りまた会えると思います。最高の思い出をありがとう。
「ますます湧いたキノコへの興味」(広島県・高校2年生)
森の不思議、きのこを顕微鏡と遺伝子で解明する~入門編~
独立行政法人 森林総合研究所
私は今回初めてサマー・サイエンスキャンプに参加しました。なので「本当に自分なんかが参加して良いのだろうか」「参加しても内容についていけないのではないだろうか」などというような不安の方が大きかったですが、実際に体験が始まってみると、自分でも驚くほど自然体で実習をすることができました。
初めは、研究者の方々を目の前にし、不安や緊張や期待でいっぱいで、3日間も体がもつのかと本気で心配するほどでした。そんな中、主に3人の研究者の方々を中心とし、3日間を過ごしました。私がその中で1番興味を持ったのがキノコについての話でした。私はもともと、キノコというものに興味があったわけではなく、初めは学校の微生物バイオの授業で菌の中のカビに興味を持ち、友人から「キノコもカビと同じようなもの」と聞いてから、キノコへの興味がわきました。先生の話はまさに、私が興味を持ち、知りたいと思っていたものでした。参加する前にある程度調べましたが、やはり先生から聞くと新鮮でおもしろく、すんなりと頭に入り、しかも疑問に思ったことはその場ですぐに聞くことができ、私にとっては素晴らしい時間でした。そして、そこで今まで以上にキノコに興味を持ち理解を深めた上で、キノコの胞子やヒダを顕微鏡で観察し、キノコの採取やDNA分析や増幅などを、人がするのを見るのではなく、自分自身が体験するという、とても貴重な実習をすることができました。まだ話したいことや聞きたいことも山程あります。この3日間は私にとっても将来の私にとっても、とても重要で、役立つものになったと自信を持って言うことができるものとなりました。
「サマー・サイエンスキャンプで得たもの」(東京都・高校1年生)
DNAを使って見分けるスギの品種
独立行政法人 森林総合研究所 林木育種センター
私は、このキャンプに参加して、夏休みの最後にとてもよい経験ができました。キャンプでは、女子(参加した女子は皆、東京に住んでいました)3人と友達になることができました。ちょっと人見知りだったので孤立しないか心配していましたが、1日目の夜には、今日会ったばかりとは思えないほど、意気投合してしまいました。今でも連絡をとり合っています。
そして、講義や実習、施設見学など普段では出来ないことを体験しました。特に実習では、学校にはない精密な機械や道具を実際に使用することができました。例えば、ピペットは、学校で使っているような正確には量り得ないものではなく、0.01まで量ることができるものでした。使っていると、研究者になれた気になりました。
内容も、とても充実したものでした。杉の木から取ってきた葉の先の方から、DNAを採取して、その杉の種類を調べるというものでした。私の調べたものは、3つ該当する杉があり、残念ながら、1つに絞り込むことができませんでした。同じように見える杉でも、DANがちゃんと違うのだなと思いました。
また、DNAを肉眼で見ることもできました。「家庭で出来るDAN採出」という実習で、食器を洗う洗剤やアルコールを使って湯せんをすると、ほうれん草のDANが白い糸のように見えてきました。もやもやとしたものがたくさん出てきて、家にあるものでこんなことができるのかと驚きました。
このキャンプに応募して、とてもよかったと思っています。
「自然が豊かという意味」(千葉県・高校2年生)
森林の昆虫と生物多様性~環境教育プログラムを作ってみよう~
独立行政法人 森林総合研究所 多摩森林科学園
今回の会場は、都会で孤立した森の中でした。セミや鳥の声しか聞こえない所から一歩出ると、私の住んでいる所よりも大きな街並みが見渡す限り広がっています。
私は、そこで生物多様性について学びました。生物多様性が高いとは、そこに住んでいる生き物の個体数が多い事でも、生き物の種類が多い事でもないと知りました。生物多様性が高いという事がいい事ではないという事も知りました。たとえ一種類の生き物の数が極端に多かったり少なかったりしても、多様性の高さは高くなりません。たくさんの種類の生き物がいて、しかもその生き物もだいたい同じくらいいると、多様性は高くなるのです。
けれでも、普通、自然はいろいろな生き物の数が偏っているからバランスがとれるものです。ということは、自然が豊かということと、生物が多様であるということは必ずしもイコールではないということです。
そんなことを勉強したあとで、自分の家を見てみました。確かに、森と比べると生き物の種類は少ないです。でも、自然が豊かと言えるかもしれません。チョウやハチや鳥、バッタ、トカゲ、アメンボ、カマキリ、私達でさえ知らないくらいたくさんの生き物がいます。本来の自然の姿とは異なりますが、たくさんの生き物が食物連鎖の中でお互いに助け合いながら生きています。ある意味自然が豊かなのかもしれません。
森では今までに見た事のない動植物がいました。そして自然について考えるひとつのきっかけなりそうです。このようなことをみんなが考えるようになれば、今の自然の状態が変わるようになるかもしれません。それを他の人に伝えるのに、今回の経験はとても役に立ちそうです。
「『夢』と『海』と『経験』」(愛媛県・中等教育学校6年生)
フィールド研究が地球を救う
独立行政法人 水産総合研究センター 中央水産研究所
私は小さい頃から動物が大好きでした。進路を水産に決めたのは去年の夏のことでした。「海」というこの地球のおよそ7割を占めているフィールドの奥深さに魅せられ、深海生物の生態研究をしたい、そう思うようになりました。今回は、女性のフィールド研究者の方のお話が聞けるということで応募しました。
最初の館内見学では浅海のことが主でしたが、魚にもPCR法で遺伝子を調べることができたり、イルカやクジラの年齢は歯で調べることができたりなど、様々なことを知ることができました。実際に磯生物を採集したときは、狭い範囲であんなにも多くの生物がいたこと、それを採集することの難しさ、生物同定に必要な根気強さなど、フィールド研究の模擬体験は大きな糧となりました。
また、深海生物の解剖という希少な経験ができ、「海」により興味を持ったとともに、深海にしか焦点を当てていなかったという自身の視野の狭さに気付かされました。それは、多くを学べる機会を失っているのだと痛切に実感させられるものでもあり、色々なことに目を向けようと、私自身の他のものに対する価値観を変えてくれたように感じます。
南極についてのお話は特に良い体験であったように思います。専門知識などが少ない私の疑問であっても、多岐な研究テーマとして扱うことができると言われた時には驚きました。何気ない「何故?」が研究になる。研究という一部の優れた人がやっている、と思っていたものが、こんなにも自分の身近なところにある。それはとても素晴らしいことがと感じました。
「エンジンとこのキャンプの魅力」(神奈川県・高校2年生)
最先端技術を探究する
独立行政法人 産業技術総合研究所 つくばセンター
私はスターリングエンジンを作らせていただきました。開催前に送られてきた資料はとても分厚く、とりあえず目は通したものの内容はほぼ理解できない状態で参加し、最初はかなりの戸惑いがありました。しかし、講師の方々のフレンドリーな様子のおかげで、分からなかったところもすぐ聞けるようになり、かなり知識が深まったように思います。
また、実習では厳しいダメ出しをもらいながらも、参加者全員が見事にスターリングエンジンを使っての発電に成功しました。自分が触れてもいないのに熱の変化によってどんどんホイールが加速していくと、おもわず歓声がこぼれました。その電力をつかってダイオードを光らせるにはかなりの回転数が必要で苦労しましたが、光った瞬間の感動は今でも忘れられません。
他に、フライス盤という大きな機械にも触らせていただきました。日常でそのような機械に触ることがなく、やや興奮気味の私たち。実はスターリングエンジンの部品の一部もそれで作っていると聞いて、余計にその機械に対するあこがれのようなものが強くなりました。
このサイエンスキャンプの1番の魅力は、実際に現場にいる人と質疑応答でき、現場で作っている機器に触れられることだと思います。たとえそれが自分の中で予定している未来に関わりがないようなテーマでも、非常に興味深く、強く思い出として残ることは間違いありません。
また、このキャンプに参加したことを通じて、考えているだけではなく、やりたい、と思ったことを行動に移すことの大切さにも気付くことができました。
「目に見えない地球温暖化」(宮崎県・高校2年生)
南の島から地球温暖化を考える
独立行政法人 国立環境研究所 地球環境モニタリングステーション-波照間-
「視野が広がった」「将来の夢が決まった」こんなことを思わずにはいられないキャンプだった。
私はこんなにも、充実した3日間を過ごしたことがないと言っても過言ではないほどに、このキャンプを有意義に過ごすことが出来た。波照間島でのキャンプは暑さとの戦いでもあると同時に、温暖化の影響を切実に実感できるキャンプであった。実験では波照間の海水や空気、土壌、植物をサンプリングして、二酸化炭素濃度を測定した。実験の結果は、昨年よりも確実に濃度が増していた。目で見ることができる影響には素直に温暖化は深刻化していると思えるが、目に見えない影響にはあまり深刻に感じられなかった、今までは。しかし、自分達の手で測定した目には見えない実験結果に愕然とした。私のような素人が出したデータでも温暖化の影響がグラフという形で表れている。私は目の前にあるデータを疑わずにはいられなかった。しかし、それは疑いようのない事実なのだ。映画でもあるように「不都合な真実」のタイトルの意味が初めて実感できた。私は一刻も早く行動しなければならないという思いに掻き立てられた。その思いが私の夢を確固たるものにした。私は今、誰にでも自分の夢を自信持って言うことが出来る。それは「温暖化」の改善。これは、キャンプで巡り合えた講師の先生方、同じ志を持つ仲間達と会えた、すばらしい出会いのお陰でもある。この夢は、残りの学生生活に大きく影響するだろう。
「人も自然も守りたい」(広島県・高校2年生)
生命と環境
独立行政法人 国立環境研究所
科学の発展が私たちの生活を便利で豊かなものにしてきたと信じ、人間が持つ『知恵』は本当に素晴らしいと思っていました。しかし、科学の発展が、地球温暖化などの環境問題を引き起こしているという事を知らされ、野生動物達を、動物である人間が絶滅に追いやっている事実に愕然としました。
科学を発展させた事が地球にダメージを与えてきたのだとすると、人間が科学を捨てなければ地球環境を守ることはできないのではないかと、考えていたこともありました。このまま科学の道に進む事をためらう気持ちが、いつも私の中にありました。
でも、今回のサイエンスキャンプで国立環境研究所に行かせて頂き、自然がいっぱいの美しい敷地の中で、先生方が様々な実験をされて、環境を守るために力を尽くされておられる様子を目の当たりにすることができ、また、先生方とお話をさせて頂いた中で、私もそのお手伝いがしたいと、強く感じることができました。
全国から集まった参加者との出会いも、これからの私の人生を豊かなものにしてくれることでしょう。同じことに興味を持つ同年代の人たちが、学んだ事を発表しあったり、自分の考えをみんなで議論したり。サイエンスキャンプでは、とても有意義な時を過ごさせて頂きました。
この夏の出会いを大切にしながら、将来『科学を通して、人も動物も地球環境も守れる仕事がしたい!』という夢を追いかけていきたいと思います。
「建築と環境問題」(静岡県・高校2年生)
地球温暖化防止のためのワークショップ
清水建設株式会社 技術研究所
私は建築という分野に興味があり、このプログラムに参加させていただきました。科学技術研究所の施設内を見学させていただいた時は驚くことばかりでした。ビオトープでは3㎝しか自然の土が使われていませんでした。これで建物への負担を減らし、さらには、雨水を人工の土の下に貯めることができるため、水をあげるのにも水道代がほとんどかかりません。また、グラデーションブラインドは緯度・経度・日時によってブラインドの角度を変えることで天井に光を当て、蛍光灯の使用量を減らすことができます。
また、普段の生活の中で自分が排出しているCO2の量を計算してみると、思っていたよりも多くのCO2を排出していることがわかりました。そして、自らが排出したCO2の分を減らすためにカーボンオフセットというものがあることを知りました。専用の年賀状やインターネットを利用することで、環境保全に協力できると知り、やってみようと思いました。
廃棄物のガス化実験では、コーヒーガラとシュレッダー紙ゴミをガス化しました。ゴミとなり捨てられてしまうものからガスができることにとても驚きました。ガス化すれば廃棄物処理によって排出されるであろうCO2をなくすことができ、ガスはエネルギーとして利用できるため、他のエネルギーの使用を減らすことができます。だから早く身近な所で廃棄物のガス化ができるようになってほしいです。
この3日間、様々な考えを持った人達と出会い、意見を交換することによって知識の世界が少し広がったと思います。とても充実した3日間でした。
「3日間のサイエンスキャンプを終えて」(大阪府・高校2年生)
落下塔を利用した微小重力実験の体験
株式会社日本無重量総合研究所 無重量研究センター
今回初めて参加させていただいて、心の底から良かったと思っています。特におもしろかったのは、落下実験で、落下させるまでの作業やカプセルの組み立てで、その場で見ないとすごさが分からないような事を見学したことです。実験では、はね返る球の運動を実際に行いました。初めは、基礎となる通常重力環境ではね返る球を高速度カメラで見て、それから無重力環境ではね返る球の落下実験を行いました。
私の学校では、受験がないため、3年で物理を学ぶのですが、今回その物理的な式や用語が出てきて、初めの話はあまり分かりませんでした。ですが、少しですが、理解できました。落下実験は2回ほど落下させて、自分の班は両方成功でした。それにより正確なデータが得られました。わずかなズレはあったのですが、それに近いデータを得られました。このデータを得られたのも、サポートして下さった会場の方や、アドバイザーの方、そして班で一緒に実験をした3人のおかげです。
科学が好きだと言っていても、やはりまだまだ知らない事ばかりで、宇宙の事に関しても、「そうだったんですか」、と思うことばかりです。でも、嫌いになってはいません。これをきっかけに、もっともっと沢山学んでみたいと思いました。
今回1番興味を持ったのは、通常重力状態と無重量状態との違いがあまり見られなかったことです。私はまだ、はっきり理解していなかったのですが、徐々に面白くなってきました。この3日間、貴重な体験をさせていただいて本当にありがとうございました。これを機会に、将来の夢に生かしていきたいと思っています。理科が、宇宙が以前より、大好きになりました。
「人間の声のような“音声”にびっくり」(山口県・高校1年生)
未来の産業を体験しよう!
株式会社日立製作所 中央研究所
今回、日立製作所でのサイエンスキャンプに参加して、ミューチップや音声プログラムなど、最先端の技術を体験させていただき、日ごろの学校生活ではとても学ぶことのできないことをたくさん学ぶことができました。中でも特に”音声”の講義と実習に興味をもちました。一つの音としての単位がアルファベットであることに少し驚かされてしまったり、普段音の判断は耳でしていると思っていたのに、目でも無意識に判断しているというのがわかったり、日常生活であたり前に使っている言葉はとても精密にできているのだなあと改めて考えさせられました。また、音声の作成実習では、一つの文を作り、その文で使った平がなをつなげて一つの言葉を作ったのですが、なかなか人間がしゃべっているようには作ることができず、あとから聞かされたアナウンサーの声でつくった本当に人間の声のような音声に、びっくりしました。
今回のサイエンスキャンプに参加していた人達と話していて、皆自分の意見をきちんと持っていたのが、とても印象深かったです。自分と同じ意見の人がいれば、違う人もいる、そんなことあたり前のはずなのに、なぜかあらためて深く考えさせられたような気がします。3日間のサイエンスキャンプは、とても有意義なものとなりました。この貴重な体験を自分の将来に生かして生きたいと思います。